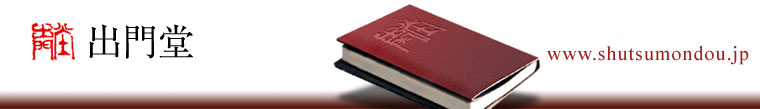佐賀の出版元 出門堂 | 2008年09月
2008年09月06日
「あ~れ~~」にも技術が要る?!
制作中の本の取材で、ある着付けの先生を訪ねたときのこと。
時代劇などで目にする、女性が着物の帯をほどかれる場面。実はそのシーンには着付けの技術が関係しているそうです。最近の着付け方法は様々な留め具を使用して何本もの紐でしばり、着崩れしないように保っているため、一度でほどくことはできないそうです。その先生の着付けは、一切それらの留め具を使用しません。ですので、帯をほどく時は「あ~れ~~」状態でとけるそうです。しかし、着崩れしにくいながらも圧迫感がないので長く着物を着ていられるそうです。本来の着物文化のうえではあたりまえのことだったのかもしれません。
何気なく見ていた時代劇にも日本の文化の巧みな技が隠されていたのですね。
ただし、女性が人前で帯をほどくのは貞節がないことを意味するため絶対にしないでほしいとおっしゃっていました。
時代劇などで目にする、女性が着物の帯をほどかれる場面。実はそのシーンには着付けの技術が関係しているそうです。最近の着付け方法は様々な留め具を使用して何本もの紐でしばり、着崩れしないように保っているため、一度でほどくことはできないそうです。その先生の着付けは、一切それらの留め具を使用しません。ですので、帯をほどく時は「あ~れ~~」状態でとけるそうです。しかし、着崩れしにくいながらも圧迫感がないので長く着物を着ていられるそうです。本来の着物文化のうえではあたりまえのことだったのかもしれません。
何気なく見ていた時代劇にも日本の文化の巧みな技が隠されていたのですね。
ただし、女性が人前で帯をほどくのは貞節がないことを意味するため絶対にしないでほしいとおっしゃっていました。
(M)
2008年09月05日
イトモロコ(佐賀の淡水魚)
イトモロコ。
あまり大きくならないようで、写真のものも5㎝ぐらいです。
いつも水槽の下の方にいて、
他の種類とちがって、
餌を求めて水面に浮上する動きはほとんど見せません。
背中に黒い模様があるので、すぐにイトモロコと知れます。
からだの流線型が最も美しいと思っています。

(X)
あまり大きくならないようで、写真のものも5㎝ぐらいです。
いつも水槽の下の方にいて、
他の種類とちがって、
餌を求めて水面に浮上する動きはほとんど見せません。
背中に黒い模様があるので、すぐにイトモロコと知れます。
からだの流線型が最も美しいと思っています。

(X)
2008年09月02日
オイカワの雄
オイカワの雄。
オイカワを食した感想は、「うまい」「まずい」と両極を耳にします。
私も10㎝弱のオイカワを天ぷらにしたことがありますが、
けっこうおいしく食べました。
雄は繁殖期になると縞模様が青みを増し、
ひれの先に赤い色がさし、
大変派手な姿になります。
もっと大きく雄壮な雄を獲ったことがありますが、
いずれもすごいジャンプ力で、
バケツから川へ帰っていきました。

(X)
オイカワを食した感想は、「うまい」「まずい」と両極を耳にします。
私も10㎝弱のオイカワを天ぷらにしたことがありますが、
けっこうおいしく食べました。
雄は繁殖期になると縞模様が青みを増し、
ひれの先に赤い色がさし、
大変派手な姿になります。
もっと大きく雄壮な雄を獲ったことがありますが、
いずれもすごいジャンプ力で、
バケツから川へ帰っていきました。

(X)
2008年09月01日
第一級の知識人 古賀精里・侗庵
8月23日付の佐賀新聞紙上で、小社の新刊『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』(梅澤秀夫著)が紹介されました。
記事には次のようにあります。
戦前までは、江戸時代屈指の知識人として著名であった古賀精里・侗庵父子ですが、この半世紀ほどの間に教科書に載っても小さく扱われる程度となり、その名を知る人もすっかり減ってしまったようです。半世紀という時間にどのような変化が起こっているのでしょう。
古賀精里・侗庵は、二代にわたり江戸の昌平坂学問所で教授を務めた佐賀藩出身の儒学者です。ペリー来航以降、日本における海外への意識が高まったことは知られていますが、その半世紀も前に日本にとって外交や海防がいかに重要であるかということを説いています。すでにこのころ対ロシア政策などを具体的に論じています。
「半世紀」とは、私たちを取り巻く環境を大きく変えうる歳月かもしれません。それでも彼らの考えたことを現在こうして知ることができるのは、先人たちがそれを語り継ぎ、遺してきたことの証しでもあります。
この『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』をはじめとして、肥前佐賀文庫では長期のビジョンで読者の方々に問題提起ができればと希っております。
記事には次のようにあります。
高校の歴史教科書にもほとんど出ることがない二人だが、著者の梅澤教授は「歴史をきちんと理解するためには、昔の人の精神世界に踏み込んだ思想史の分野を知ることが必要」と、執筆の動機をあとがきで述べている。偉業を後世に語り継ぐ役割だけでなく、日本人の思想を理解するうえで重要な一冊となっている。
戦前までは、江戸時代屈指の知識人として著名であった古賀精里・侗庵父子ですが、この半世紀ほどの間に教科書に載っても小さく扱われる程度となり、その名を知る人もすっかり減ってしまったようです。半世紀という時間にどのような変化が起こっているのでしょう。
古賀精里・侗庵は、二代にわたり江戸の昌平坂学問所で教授を務めた佐賀藩出身の儒学者です。ペリー来航以降、日本における海外への意識が高まったことは知られていますが、その半世紀も前に日本にとって外交や海防がいかに重要であるかということを説いています。すでにこのころ対ロシア政策などを具体的に論じています。
「半世紀」とは、私たちを取り巻く環境を大きく変えうる歳月かもしれません。それでも彼らの考えたことを現在こうして知ることができるのは、先人たちがそれを語り継ぎ、遺してきたことの証しでもあります。
この『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』をはじめとして、肥前佐賀文庫では長期のビジョンで読者の方々に問題提起ができればと希っております。
(A子)