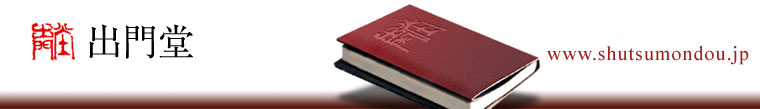佐賀の出版元 出門堂 | 2008年05月
2008年05月31日
編集見習い日記-その6-
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
出門堂に入門してはや一年、私が企画の段階から関わってきたはじめての本が、まもなく刊行されます。昨年、『佐賀読本』が書店に並んでいるのを見たときにもうれしさがこみ上げてきたのを覚えていますが、やはり一冊の本ができあがっていく過程をはじめからみてくると、一入の感慨があります。
このエッセイには、昭和のはじめ、佐賀市の本庄という小さな町に育った少女が出会った日々の出来事がつづられています。本書のいたるところにあふれる著者の思いは、同じ頃を生きた人々はもちろん、当時を知らない私たち若い世代にもしっかりと伝わってきます。
提灯を片手に暗い夜道をいっしょに歩いてくれた小父さんのこと、いまも心のひとすみにある父と「私」の「狸の薬局」のこと、少女の日常のひとつひとつに触れると、彼女自身や周りの大人たちのやさしいぬくもりに包まれるようです。希薄になってきたといわれる「大人」と「子供」のつながりが、昭和のはじめ、少女の周りにたしかにあったのだということがひしひしと感じられます。あたたかくて、なつかしくて、そして少しせつない36の掌篇です。
6月20日に発行予定の出門堂の新刊です。ご期待下さい。

著者 小山内富子
挿絵 緒方義彦
目次
なしてかの道
大人はしっきゃ親代わりたい
私が斜視だったころのことなど
寒稽古
メダカの御冥福
功名の雨傘
キャーモンの日
出直し喧嘩
戻り橋
もぐら打ち
徒らに机上の装飾とする勿れ
空を飛んだ鯛
村の巡査と一升の米
ぜんもんさんの宴
父の兄弟と古代オリンピック
狸の薬局
ホッテントットの化粧料
千人針と野菜爆弾
さんとく銀行
毬子を抱いて戻った友達
父の女装
色彩二題
鼈甲の煙草ケース
魚の哲学
文字のない墓石
遠い眺め
海辺のハイジ
方言賛歌
ピンクの雨
虚構であったとしても
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
乳母車
道を急ぐことはない
菩提寺の本堂で
窓のない蔵の窓
五文字の電報
出門堂に入門してはや一年、私が企画の段階から関わってきたはじめての本が、まもなく刊行されます。昨年、『佐賀読本』が書店に並んでいるのを見たときにもうれしさがこみ上げてきたのを覚えていますが、やはり一冊の本ができあがっていく過程をはじめからみてくると、一入の感慨があります。
このエッセイには、昭和のはじめ、佐賀市の本庄という小さな町に育った少女が出会った日々の出来事がつづられています。本書のいたるところにあふれる著者の思いは、同じ頃を生きた人々はもちろん、当時を知らない私たち若い世代にもしっかりと伝わってきます。
提灯を片手に暗い夜道をいっしょに歩いてくれた小父さんのこと、いまも心のひとすみにある父と「私」の「狸の薬局」のこと、少女の日常のひとつひとつに触れると、彼女自身や周りの大人たちのやさしいぬくもりに包まれるようです。希薄になってきたといわれる「大人」と「子供」のつながりが、昭和のはじめ、少女の周りにたしかにあったのだということがひしひしと感じられます。あたたかくて、なつかしくて、そして少しせつない36の掌篇です。
6月20日に発行予定の出門堂の新刊です。ご期待下さい。

著者 小山内富子
挿絵 緒方義彦
目次
なしてかの道
大人はしっきゃ親代わりたい
私が斜視だったころのことなど
寒稽古
メダカの御冥福
功名の雨傘
キャーモンの日
出直し喧嘩
戻り橋
もぐら打ち
徒らに机上の装飾とする勿れ
空を飛んだ鯛
村の巡査と一升の米
ぜんもんさんの宴
父の兄弟と古代オリンピック
狸の薬局
ホッテントットの化粧料
千人針と野菜爆弾
さんとく銀行
毬子を抱いて戻った友達
父の女装
色彩二題
鼈甲の煙草ケース
魚の哲学
文字のない墓石
遠い眺め
海辺のハイジ
方言賛歌
ピンクの雨
虚構であったとしても
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
乳母車
道を急ぐことはない
菩提寺の本堂で
窓のない蔵の窓
五文字の電報
(A子)
2008年05月15日
「お玉ヶ池種痘所」開設150年
1858年(安政5年)5月7日、当時の日本で最高の死亡率をほこった天然痘の治療のため東京に「お玉ヶ池種痘所」が開設されました。今年は開設されてから150年にあたります。
この「お玉ヶ池種痘所」は現在の東京大学医学部の前進といわれています。開設と運営については、伊東玄朴(佐賀県神埼町仁比山出身)を中心とする蘭方医たちが尽力していたそうです。
そして、天然痘治療に大きな成果をみせ、撲滅へのきっかけとなる牛痘接種を日本ではじめて成功させたのは長崎出身で佐賀藩医であった楢林宗建です。牛痘接種成功への舞台裏を自ら医師である深瀬泰旦先生が『わが国はじめての牛痘種痘 楢林宗建』で詳しく書かれていますのでぜひご覧ください。
本文より少し抜粋
……蘭方医たちの牛痘接種法への憧憬は、日毎にたかまっていた。とくに佐賀藩では弘化三年の天然痘の大流行を機に、牛痘接種法への関心はいやが上にもたかまった。江戸在府の藩医伊東玄朴は、牛痘苗の移入を藩主鍋島直正に進言し、直正は長崎在住の藩医に痘苗入手の指示をあたえた。
当時の人の天然痘撲滅への強い思いが感じられます。
この「お玉ヶ池種痘所」は現在の東京大学医学部の前進といわれています。開設と運営については、伊東玄朴(佐賀県神埼町仁比山出身)を中心とする蘭方医たちが尽力していたそうです。
そして、天然痘治療に大きな成果をみせ、撲滅へのきっかけとなる牛痘接種を日本ではじめて成功させたのは長崎出身で佐賀藩医であった楢林宗建です。牛痘接種成功への舞台裏を自ら医師である深瀬泰旦先生が『わが国はじめての牛痘種痘 楢林宗建』で詳しく書かれていますのでぜひご覧ください。
本文より少し抜粋
……蘭方医たちの牛痘接種法への憧憬は、日毎にたかまっていた。とくに佐賀藩では弘化三年の天然痘の大流行を機に、牛痘接種法への関心はいやが上にもたかまった。江戸在府の藩医伊東玄朴は、牛痘苗の移入を藩主鍋島直正に進言し、直正は長崎在住の藩医に痘苗入手の指示をあたえた。
当時の人の天然痘撲滅への強い思いが感じられます。
(M)
2008年05月04日
枝吉神陽が会った人々6 五十嵐三省
3回目に取り上げた藤森弘庵ともに五十嵐三省とも、この旅の中で交遊しています。弘化3年(1846)3月頃と思われます。
さて、この五十嵐三省ですが、「五十嵐三省墓誌」なるものがあり、『事実文編』七六に収録されています。撰文は木原元礼です。それによると、
文政2年(1819)~明治7年(1874)。名を儀一、別号を愛山。常陸土浦の人。土屋氏に仕える。木原とともに藤森弘庵のもとで学んだ。昌平坂学問所にも留学した。
ということがわかります。このような人物たちがどの程度顕彰されているのか?
常陽新聞新社『民話一○○話 土浦ものがたり』の中に取り上げられているようですが未読です。
神陽の足取りを追ってみると、昌平坂学問所の人物が藩をこえて交際が密であったことがよくわかります。
さて、この五十嵐三省ですが、「五十嵐三省墓誌」なるものがあり、『事実文編』七六に収録されています。撰文は木原元礼です。それによると、
文政2年(1819)~明治7年(1874)。名を儀一、別号を愛山。常陸土浦の人。土屋氏に仕える。木原とともに藤森弘庵のもとで学んだ。昌平坂学問所にも留学した。
ということがわかります。このような人物たちがどの程度顕彰されているのか?
常陽新聞新社『民話一○○話 土浦ものがたり』の中に取り上げられているようですが未読です。
神陽の足取りを追ってみると、昌平坂学問所の人物が藩をこえて交際が密であったことがよくわかります。
2008年05月01日
一年ぶりのリベンジ
先週の土曜日、佐賀市大和町にある「華蔵庵」へ行ってきました。
ご存知の方も多いと思いますが、ここは湛然和尚が晩年住まいとしていた跡です。湛然和尚とは『葉隠』の口述者である山本常朝の師として大きな影響を与えた人です。現在は、このような塔がたててありました。

実は、約一年前にも出門堂発行の「老いと死の超克――わが葉隠」の取材でこの場所を探していました。1時間以上も近辺を探し回ったあげく、たどりつくことができずに諦めたのですが、今回は難なく行きつけました。というのも、「華蔵庵」入口に去年の取材時にはあきらかになかった、立派な案内板が設置されていて容易に発見できたのです。どなたか、同じ思いをされて設置していただくことになったのかわかりませんが、名古屋からのお客様を案内していたので非常に助かりました。
「華蔵庵」は杉林に囲まれた小高い山の中にありました。鳥の声と風にゆれる杉の葉の音しか聞こえない静かな場所です。ここで湛然和尚と山本常朝はどんな話をしていたのか……
去年の取材時に同じ大和町にある石田一鼎の閑居跡も訪れたのですが、ここも探しあてるのに苦労した場所でした。全ての史跡の整備がなされるのは難しいかも知れませんが、郷土の遺産を大切にしていきたいと思った一日でした。
取材箇所もろくにたどり着けないなんて……まだまだ詰めがアマイ編集の日々です。
ちなみに「華蔵庵」はこちらです。
国道263号線を三瀬峠方面へ向かって大和町の三反田交差点を左折すると右手に画廊があります。
そのすぐ脇の小道を登って左の道へ進み、ばらくしたら「華蔵庵」の案内がみえます。
ご存知の方も多いと思いますが、ここは湛然和尚が晩年住まいとしていた跡です。湛然和尚とは『葉隠』の口述者である山本常朝の師として大きな影響を与えた人です。現在は、このような塔がたててありました。

実は、約一年前にも出門堂発行の「老いと死の超克――わが葉隠」の取材でこの場所を探していました。1時間以上も近辺を探し回ったあげく、たどりつくことができずに諦めたのですが、今回は難なく行きつけました。というのも、「華蔵庵」入口に去年の取材時にはあきらかになかった、立派な案内板が設置されていて容易に発見できたのです。どなたか、同じ思いをされて設置していただくことになったのかわかりませんが、名古屋からのお客様を案内していたので非常に助かりました。
「華蔵庵」は杉林に囲まれた小高い山の中にありました。鳥の声と風にゆれる杉の葉の音しか聞こえない静かな場所です。ここで湛然和尚と山本常朝はどんな話をしていたのか……
去年の取材時に同じ大和町にある石田一鼎の閑居跡も訪れたのですが、ここも探しあてるのに苦労した場所でした。全ての史跡の整備がなされるのは難しいかも知れませんが、郷土の遺産を大切にしていきたいと思った一日でした。
取材箇所もろくにたどり着けないなんて……まだまだ詰めがアマイ編集の日々です。
ちなみに「華蔵庵」はこちらです。
国道263号線を三瀬峠方面へ向かって大和町の三反田交差点を左折すると右手に画廊があります。
そのすぐ脇の小道を登って左の道へ進み、ばらくしたら「華蔵庵」の案内がみえます。
(M)