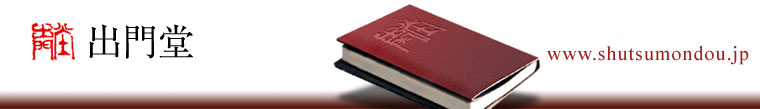佐賀の出版元 出門堂 | 今日のひとこと
2008年12月12日
『よみかき論語』が好評です
新刊『よみかき論語』が好評です。
論語の原文の表記が新鮮だと評されますが、本書の原文はすべて、熟練の書家が初唐の楷書に倣って揮毫しています。
私たちは大量の活字の中で生活していますが、もともと文字の美意識は毛筆で書かれた書の歴史に基づいています。
美しい楷書体のテキストで「よみ」「かき」の素養を育みたいものです。
(X)
論語の原文の表記が新鮮だと評されますが、本書の原文はすべて、熟練の書家が初唐の楷書に倣って揮毫しています。
私たちは大量の活字の中で生活していますが、もともと文字の美意識は毛筆で書かれた書の歴史に基づいています。
美しい楷書体のテキストで「よみ」「かき」の素養を育みたいものです。
(X)
2008年10月11日
小松帯刀について
新聞広告で瀬野富吉『幻の宰相 小松帯刀伝』が宮帯出版社から復刊されたことを知りました。
この本はもともと昭和60年に発行されたもので、入手がむずかしい本でした。
私がこの本を知ったのは、今年亡くなった草森紳一氏から、「小松帯刀について書かれた本が出ているはずだが、手に入れ損ねている」と聞いたことからです。いろいろたどって瀬野氏のご遺族から上下2冊を2セット譲ってもらい、1セットを草森氏にお送りしました。
今回の復刊は、NHK大河ドラマによって小松帯刀に注目が集まったことによるだろうと思われます。しかし、この本の背後には、瀬野氏や小松帯刀顕彰会、大河ドラマとは無縁の郷土の人々の、おそらく多大なご苦労があったことを想像します。
序文の末尾で原口泉氏(鹿児島大学助教授〈当時〉)はこのように語っておられます。
重い言葉です。
さて、佐賀の版元である出門堂から紹介したい記事があります。小松帯刀という人物について大隈重信が語った言葉です。
長くなりましたが、大隈の個人的な見解ながら、小松帯刀という人物の魅力に触れたような気になり、すがすがしい気持ちになります。(X)
この本はもともと昭和60年に発行されたもので、入手がむずかしい本でした。
私がこの本を知ったのは、今年亡くなった草森紳一氏から、「小松帯刀について書かれた本が出ているはずだが、手に入れ損ねている」と聞いたことからです。いろいろたどって瀬野氏のご遺族から上下2冊を2セット譲ってもらい、1セットを草森氏にお送りしました。
今回の復刊は、NHK大河ドラマによって小松帯刀に注目が集まったことによるだろうと思われます。しかし、この本の背後には、瀬野氏や小松帯刀顕彰会、大河ドラマとは無縁の郷土の人々の、おそらく多大なご苦労があったことを想像します。
序文の末尾で原口泉氏(鹿児島大学助教授〈当時〉)はこのように語っておられます。
私達は、小松を育んだ薩摩の風土をあらためて見直すことから、将来への方向性を探っていなければならない。
重い言葉です。
さて、佐賀の版元である出門堂から紹介したい記事があります。小松帯刀という人物について大隈重信が語った言葉です。
小松はわたしたちの先輩であると共に友達でもあった。見かけは堂々として口も達者であり、少しは学識もあって、気性も卑屈ではなかった。その上薩摩藩の名家として、世間からは非常に信頼されていたから、外国の副知官事としては最も適任者であった。好事魔が多く、桂や蘭は折れ易いと云うことがある。不幸にも天は秀才に幸いせず、小松は副知官事に任じられる前から、腎臓病にかかり、職にあること数ヵ月で臥床した。内治、外交、国家の将来について、身体中に満ちあふれた素晴らしい計画を持ちながら、あきらめ切れぬ涙を呑んで死んでしまったのである。ああ、悲しいことではないか。そしてまた国家や国民の不幸でもないか。そうして彼のあとを継いだものは誰であったか。小松が推薦した人は誰であったか。思うに、その当時は薩摩と云い、長州といい、いずれも戦勝の余勢にのって、その権力は非常に盛んであった。従って政府の官吏や、地方の役人の中にも薩長の出身者が多かった。外交官だけが除けもの扱いにはされていなかった。寺島陶蔵(宗則)、町田民部(久成)、五代才助(友厚)は薩摩藩の人で外国官判事であった。長州藩の井上聞多(馨)、土佐藩の後藤象二郎(元曄)も同じ職であった。これらの人たちは、多くは小松の推薦でその地位を占めたもので、いずれもわたしの先輩であった。小松が腎臓病に罹ってもう一度起ち上がることが出来ないのを知って、その後任者を推薦しようとした時、これらの人たちから引き抜くのは、必ずしも私心や情実によるとは云えないだろう。ところが彼は終にこれらの人々を引き抜かず、この大隈重信を推薦しようとは、わたしも他人もみな予想外のことであった。
わたしは小松と古くから交わっていたものではない。維新の前後、わずか三、四回会っただけである。わたしは別にすぐれた外交上の学識や技能を持っているわけでもない。まして熟達した経験や、世に知られた功績を持つものでもない。もし有るとしたなら、横浜と江戸の間で、横須賀の回復や、軍艦兵器の受取りに走り歩き、また長崎の耶蘇教問題について談判に当たったなどで、いささか経験し、功績を得たにすぎなかった。ただこれだけであった。だからこれだけで、薩長の大変な権勢をしのぎ、先輩の人たちをさしおいて、直ちに小松の後をつぐ値打がどうしてあるだろうか。それなのに小松は他のものを差しおいてわたしを推薦し、当時の政府は、その忠実な意見をうけ入れて、小松の死後すぐにわたしを外国官の副知官事に任命するようになった。誰も意外だと思うたことだろう。今から考えて見ると、小松は事を処理する時に公平を旨としていた。公に対して一片の私心も挟まなかったのである。「同郷がなんだ、縁故がなんだ。藩の係り合いもどうでもよろしい。情実など取るに足りない、ただ才能があるものを用い、適任者を選ぶだけだ。」と。これが小松が公に処して人を採用する本心であった。当時世間の人たちが凡て私欲をあさり、私利に走る時、このような名士がいたのだから、人々はみなこれを尊敬したのである。国家の重席に連なり、重要な職務を行うたもので、小松のように公平無私の心を持って天下に臨み、政務をとったならば、官民の衝突は今のように激しくならず、かつ世の志士や道徳家が最も非難した、藩の関係やその情実による弊害は起こらず、維新の改革と、大業の進歩は一段と見るべきものがあり、明治維新の歴史は一層光を放ったであろう。惜しいかな、小松は早く逝いてそのあとを追うものがなく、藩閥とか情実とかいう汚らわしい言葉が潔白な世間の人たちの口から出て、已むを得ず時の政府を攻撃するようになったのである。
わたしがこう云うのは、小松が推薦してくれた恩に対して礼を云うための私情から出たものではない。本当に公平で私する心がないことが、ハッキリしているからである。歴史を読み、むかしを想い、ただ一すじにこれを思うごとに、限りない感慨が胸中を行き来するのである。
(『大隈伯昔日譚』早大出版部)
長くなりましたが、大隈の個人的な見解ながら、小松帯刀という人物の魅力に触れたような気になり、すがすがしい気持ちになります。(X)
2008年10月09日
秋の展覧会
10月3日から唐津市にある佐賀県立名護屋城博物館で寄贈記念展「洪浩然 忍・忘れず」が開催されています。
この、「洪浩然」という人は小社発行の『佐賀読本』(金子信二著)にも登場しています。豊臣秀吉の朝鮮出兵で鍋島直茂らによって12、13歳で朝鮮から日本へ連れてこられた洪浩然ですが、その生涯のほとんどを佐賀で過ごしています。
洪浩然は、直茂の子の勝茂とともに育てられ、やがて京都で学ぶことを許され、佐賀藩の儒者となって多くの影響をのこしました。70歳のとき、洪浩然は帰国を願い出て、いったんは許されたのですが、洪浩然を惜しむ勝茂によって許可は取り消され、結局、浩然は帰国の念願を果たすことはできませんでした。
洪浩然の願いは叶わず日本で余生を送るのですが、共に育った勝茂が亡くなると自分も後を追って殉死してしまいます。
今度の展覧会では洪浩然の書も展示されており、「こぶ浩然」とよばれた、その印象的な書は書家の石川九楊氏が『蒼海副島種臣書』(二玄社)のなかで、明治時代の政治家であり、書家でもある副島種臣も影響をうけたのではないかと推測しています。
また、『早すぎた幕府御儒者の外交論古賀精里・侗庵』のなかで洪家の跡継ぎとして佐賀藩の儒学者、古賀精里の二男(洪晋城)を養子にむかえたとあります。この古賀精里の長男は幕末佐賀藩の改革の中心にいた古賀穀堂であり、三男は父親の精里とともに江戸の昌平坂学問所の教授となった古賀侗庵です。
この、「洪浩然」という人は小社発行の『佐賀読本』(金子信二著)にも登場しています。豊臣秀吉の朝鮮出兵で鍋島直茂らによって12、13歳で朝鮮から日本へ連れてこられた洪浩然ですが、その生涯のほとんどを佐賀で過ごしています。
洪浩然は、直茂の子の勝茂とともに育てられ、やがて京都で学ぶことを許され、佐賀藩の儒者となって多くの影響をのこしました。70歳のとき、洪浩然は帰国を願い出て、いったんは許されたのですが、洪浩然を惜しむ勝茂によって許可は取り消され、結局、浩然は帰国の念願を果たすことはできませんでした。
(『佐賀読本』より)
洪浩然の願いは叶わず日本で余生を送るのですが、共に育った勝茂が亡くなると自分も後を追って殉死してしまいます。
今度の展覧会では洪浩然の書も展示されており、「こぶ浩然」とよばれた、その印象的な書は書家の石川九楊氏が『蒼海副島種臣書』(二玄社)のなかで、明治時代の政治家であり、書家でもある副島種臣も影響をうけたのではないかと推測しています。
また、『早すぎた幕府御儒者の外交論古賀精里・侗庵』のなかで洪家の跡継ぎとして佐賀藩の儒学者、古賀精里の二男(洪晋城)を養子にむかえたとあります。この古賀精里の長男は幕末佐賀藩の改革の中心にいた古賀穀堂であり、三男は父親の精里とともに江戸の昌平坂学問所の教授となった古賀侗庵です。
(M)
2008年09月01日
第一級の知識人 古賀精里・侗庵
8月23日付の佐賀新聞紙上で、小社の新刊『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』(梅澤秀夫著)が紹介されました。
記事には次のようにあります。
戦前までは、江戸時代屈指の知識人として著名であった古賀精里・侗庵父子ですが、この半世紀ほどの間に教科書に載っても小さく扱われる程度となり、その名を知る人もすっかり減ってしまったようです。半世紀という時間にどのような変化が起こっているのでしょう。
古賀精里・侗庵は、二代にわたり江戸の昌平坂学問所で教授を務めた佐賀藩出身の儒学者です。ペリー来航以降、日本における海外への意識が高まったことは知られていますが、その半世紀も前に日本にとって外交や海防がいかに重要であるかということを説いています。すでにこのころ対ロシア政策などを具体的に論じています。
「半世紀」とは、私たちを取り巻く環境を大きく変えうる歳月かもしれません。それでも彼らの考えたことを現在こうして知ることができるのは、先人たちがそれを語り継ぎ、遺してきたことの証しでもあります。
この『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』をはじめとして、肥前佐賀文庫では長期のビジョンで読者の方々に問題提起ができればと希っております。
記事には次のようにあります。
高校の歴史教科書にもほとんど出ることがない二人だが、著者の梅澤教授は「歴史をきちんと理解するためには、昔の人の精神世界に踏み込んだ思想史の分野を知ることが必要」と、執筆の動機をあとがきで述べている。偉業を後世に語り継ぐ役割だけでなく、日本人の思想を理解するうえで重要な一冊となっている。
戦前までは、江戸時代屈指の知識人として著名であった古賀精里・侗庵父子ですが、この半世紀ほどの間に教科書に載っても小さく扱われる程度となり、その名を知る人もすっかり減ってしまったようです。半世紀という時間にどのような変化が起こっているのでしょう。
古賀精里・侗庵は、二代にわたり江戸の昌平坂学問所で教授を務めた佐賀藩出身の儒学者です。ペリー来航以降、日本における海外への意識が高まったことは知られていますが、その半世紀も前に日本にとって外交や海防がいかに重要であるかということを説いています。すでにこのころ対ロシア政策などを具体的に論じています。
「半世紀」とは、私たちを取り巻く環境を大きく変えうる歳月かもしれません。それでも彼らの考えたことを現在こうして知ることができるのは、先人たちがそれを語り継ぎ、遺してきたことの証しでもあります。
この『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』をはじめとして、肥前佐賀文庫では長期のビジョンで読者の方々に問題提起ができればと希っております。
(A子)
2008年08月28日
ヌマムツ
ヌマムツ。

先日掲載したカワムツとそっくりですが、
あごに赤いぶつぶつがあるのが特徴です。
写真のヌマムツは15㎝以上ありますが、
これを網ですくったときには、なにごとかと思うほどの手ごたえがありました。
(X)
先日掲載したカワムツとそっくりですが、
あごに赤いぶつぶつがあるのが特徴です。
写真のヌマムツは15㎝以上ありますが、
これを網ですくったときには、なにごとかと思うほどの手ごたえがありました。
(X)
2008年08月08日
「大人はしっきゃ親代わりたい」
『「にゃーごとあろう」父の後ろ姿』の名言集。今回は、「大人はしっきゃ親代わりたい」からご紹介します。
近所の小父さんが夜道を家まで送ってくれたと話したときに、父が少女に返した言葉です。わかってはいるけれども、なかなか言える言葉ではありません。心に刻んでおこうと強く思いました。
世間の大人は、しっきゃ子供に責任ば持たんばならん。親代わりのようなもんじゃっけん
近所の小父さんが夜道を家まで送ってくれたと話したときに、父が少女に返した言葉です。わかってはいるけれども、なかなか言える言葉ではありません。心に刻んでおこうと強く思いました。
(A子)
2008年08月02日
佐賀の乱最後の激戦地「境原」の白蓮
8月2日朝の、佐賀県千代田町境原の蓮です。
「境原」という地名は佐賀の乱の最後の激戦地として有名です。
ありきたりですが、
を想起します。
「佐賀の乱」としましたが、近年「佐賀戦争」と呼ぶべきと主張する人たちもいます。
なにかのために命を賭した人々がしのばれるこの地の蓮のたたずまいの前に、
ただ静かに立っていることしかできませんでした。


(X)
「境原」という地名は佐賀の乱の最後の激戦地として有名です。
ありきたりですが、
夏草や兵どもが夢のあと(芭蕉)
を想起します。
「佐賀の乱」としましたが、近年「佐賀戦争」と呼ぶべきと主張する人たちもいます。
なにかのために命を賭した人々がしのばれるこの地の蓮のたたずまいの前に、
ただ静かに立っていることしかできませんでした。
(X)
2008年07月28日
肥前佐賀文庫003 古賀精里・侗庵が佐賀新聞有明抄に
7月28日の佐賀新聞「有明抄」で梅澤秀夫著『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』(出門堂)が取り上げられました。
ことし第一陣となる北方領土墓参団から話が起こされています。そして、
と紹介されています。また、
と述べられています。
なぜいま、古賀精里・侗庵父子について出版すべきなのか、という小社の企図の一端を代弁していただいたようにさえ思えました。(X)
ことし第一陣となる北方領土墓参団から話が起こされています。そして、
江戸時代、この北方領土へのロシアの脅威にどう対処するかを幕府に進言したのが、佐賀出身の朱子学者古賀精里・侗庵親子だった。清泉女子大学教授梅澤秀夫さんが書いた「早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵」(出門堂)を読むと、二人の先見性がよく分かる。
と紹介されています。また、
十八世紀末から十九世紀初頭にかけて、ロシアはシベリアを征服し、カムチャッカ半島から千島列島へ南下。レザノフが長崎に来て開港を迫った。精里はロシアの要求に対する想定問答集を作っている。それは和親と威嚇を両にらみした、知略に富んだものだった。
何が何でも外国人を実力排斥しようとする感情論が高まる中、冷静で合理的なものの見方をした古賀親子の存在をあらためて見直したい。
と述べられています。
なぜいま、古賀精里・侗庵父子について出版すべきなのか、という小社の企図の一端を代弁していただいたようにさえ思えました。(X)
2008年07月08日
「子供は大人が思うとっほど柔(ヤワ)やなか」
小山内富子著『「にゃーごとあろう」父の後ろ姿』の中には、すてきな言葉がたくさんあります。そのうちの一つ、少女の父親が持論としていたものです。
子供にゃ難しかけんちうて漢字ば教えんたあ、間違うとったい。教えられんやった子にとっちゃ、習いそこない損になる。子供は大人が思うとっほど柔やなか
(同書「ピンクの雨」より)
昭和初期の父の言葉を、娘の回想によって記された本です。
易しいものがもてはやされる昨今、深く考えさせられるひとことです。
子供にゃ難しかけんちうて漢字ば教えんたあ、間違うとったい。教えられんやった子にとっちゃ、習いそこない損になる。子供は大人が思うとっほど柔やなか
(同書「ピンクの雨」より)
昭和初期の父の言葉を、娘の回想によって記された本です。
易しいものがもてはやされる昨今、深く考えさせられるひとことです。
(A子)
2008年07月03日
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
小社新刊
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
について、読者からたくさんお電話をいだいています。
このようなことは小社でもはじめてです。
寄せられた感想に共通しているのは、
一気によんでしまった
むかしがなつかしい
むかしの大人は立派だった
のような言葉ですが、昨日いただいたのは、
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
というものでした。
版元としてうれしいかぎりです。
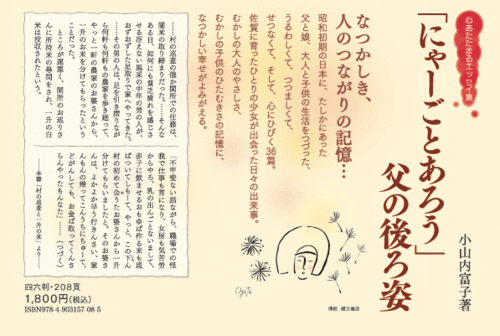
(X)
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
について、読者からたくさんお電話をいだいています。
このようなことは小社でもはじめてです。
寄せられた感想に共通しているのは、
一気によんでしまった
むかしがなつかしい
むかしの大人は立派だった
のような言葉ですが、昨日いただいたのは、
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
というものでした。
版元としてうれしいかぎりです。
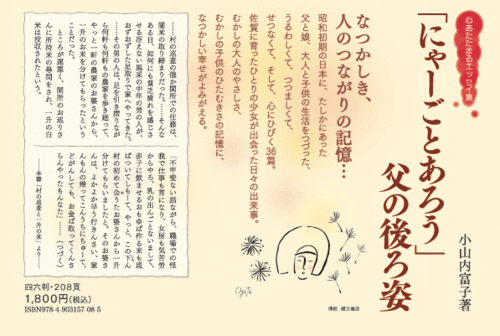
(X)
2008年05月15日
「お玉ヶ池種痘所」開設150年
1858年(安政5年)5月7日、当時の日本で最高の死亡率をほこった天然痘の治療のため東京に「お玉ヶ池種痘所」が開設されました。今年は開設されてから150年にあたります。
この「お玉ヶ池種痘所」は現在の東京大学医学部の前進といわれています。開設と運営については、伊東玄朴(佐賀県神埼町仁比山出身)を中心とする蘭方医たちが尽力していたそうです。
そして、天然痘治療に大きな成果をみせ、撲滅へのきっかけとなる牛痘接種を日本ではじめて成功させたのは長崎出身で佐賀藩医であった楢林宗建です。牛痘接種成功への舞台裏を自ら医師である深瀬泰旦先生が『わが国はじめての牛痘種痘 楢林宗建』で詳しく書かれていますのでぜひご覧ください。
本文より少し抜粋
……蘭方医たちの牛痘接種法への憧憬は、日毎にたかまっていた。とくに佐賀藩では弘化三年の天然痘の大流行を機に、牛痘接種法への関心はいやが上にもたかまった。江戸在府の藩医伊東玄朴は、牛痘苗の移入を藩主鍋島直正に進言し、直正は長崎在住の藩医に痘苗入手の指示をあたえた。
当時の人の天然痘撲滅への強い思いが感じられます。
この「お玉ヶ池種痘所」は現在の東京大学医学部の前進といわれています。開設と運営については、伊東玄朴(佐賀県神埼町仁比山出身)を中心とする蘭方医たちが尽力していたそうです。
そして、天然痘治療に大きな成果をみせ、撲滅へのきっかけとなる牛痘接種を日本ではじめて成功させたのは長崎出身で佐賀藩医であった楢林宗建です。牛痘接種成功への舞台裏を自ら医師である深瀬泰旦先生が『わが国はじめての牛痘種痘 楢林宗建』で詳しく書かれていますのでぜひご覧ください。
本文より少し抜粋
……蘭方医たちの牛痘接種法への憧憬は、日毎にたかまっていた。とくに佐賀藩では弘化三年の天然痘の大流行を機に、牛痘接種法への関心はいやが上にもたかまった。江戸在府の藩医伊東玄朴は、牛痘苗の移入を藩主鍋島直正に進言し、直正は長崎在住の藩医に痘苗入手の指示をあたえた。
当時の人の天然痘撲滅への強い思いが感じられます。
(M)
2008年04月02日
意外な発見!
昨年9月に出門堂より発行した『佐賀読本』は県内にとどまらず県外からも多くの反響の声がありました。佐賀県のさまざまなことがらを時系列を軸にからめとってまとめ、今までにありそうでなかった一冊。歴史だけでなく産業や文化などがどのように伝わってきたか、生まれたのかをわかりやすく、しかも総ルビの、ついでに言えばいろんな仕事のネタにも使えそうなすぐれものです!
(私事ながら、結婚式の引出物にもしてしまいました。これが好評でした~!)
昨年12月4日付けの朝日新聞佐賀版にも記事が掲載されました。
――今年9月に出版したところ、佐賀市内の書店売り上げランキングで、6週にわたってベスト10入りするなど評判になっている。県も職員の研修でテキストに活用することを検討している。……8世紀に編集された肥前国風土記について解説した章では、佐賀と呼ばれるようになった言い伝えを紹介。地名の由来には、思わず「ほー」とうなずかされてしまう。また、徐福渡来伝説や葉隠など佐賀にゆかりのあるキーワードも解説。佐賀の温泉やお菓子も取りあげている。――
と紹介されています。
編集に携わった私も長年佐賀に住んでいるのに知らないことばかりで、新たな佐賀の魅力にひかれています。
この春、新社会人となる方々も『佐賀読本』で意外な発見があるかもしれませんよ。
そして……先週末、草森紳一さん(評論家)の訃報がとびこんできました。
草森さんは出門堂での出版の予定もたくさんあったのですが、わが編集長は仕事をこえてやりとりしており、草森さんにぞっこんでした。この報せを受けてからは日を追うごとにため息をくりかえしています。
心よりご冥福をお祈りします。
(私事ながら、結婚式の引出物にもしてしまいました。これが好評でした~!)
昨年12月4日付けの朝日新聞佐賀版にも記事が掲載されました。
――今年9月に出版したところ、佐賀市内の書店売り上げランキングで、6週にわたってベスト10入りするなど評判になっている。県も職員の研修でテキストに活用することを検討している。……8世紀に編集された肥前国風土記について解説した章では、佐賀と呼ばれるようになった言い伝えを紹介。地名の由来には、思わず「ほー」とうなずかされてしまう。また、徐福渡来伝説や葉隠など佐賀にゆかりのあるキーワードも解説。佐賀の温泉やお菓子も取りあげている。――
と紹介されています。
編集に携わった私も長年佐賀に住んでいるのに知らないことばかりで、新たな佐賀の魅力にひかれています。
この春、新社会人となる方々も『佐賀読本』で意外な発見があるかもしれませんよ。
そして……先週末、草森紳一さん(評論家)の訃報がとびこんできました。
草森さんは出門堂での出版の予定もたくさんあったのですが、わが編集長は仕事をこえてやりとりしており、草森さんにぞっこんでした。この報せを受けてからは日を追うごとにため息をくりかえしています。
心よりご冥福をお祈りします。
タグ :佐賀ガイドブック