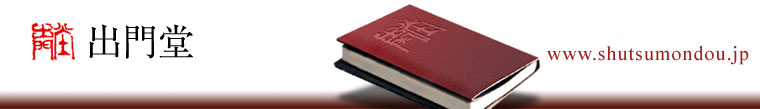佐賀の出版元 出門堂 | 2008年04月
2008年04月21日
編集見習い日記-その5-
先週末の佐賀は良く晴れたので、太良町までドライブに行ってきました。佐賀県の西南部に位置する有明海に面した町で、車を降りると潮の香りがほんわりと漂ってきます。ちょうど潮が引いて、広大な干潟が広がっていました。見ると、干潟の上に動くものがあります。ムツゴロウです。それもものすごい数の。
ムツゴロウは地域のシンボルマークにもなっていますし、また昨年小社で刊行した『佐賀読本』の編集にあたってもたくさんの写真を見ていたので、すっかり見たつもりになっていましたが、じつは私はそれまで本物のムツゴロウを見たことがありませんでした。そして、見たことがないというその事実に、はじめて気がついたのです。生まれは長崎、現在は佐賀、有明海にこれほど近い場所にいながら、いかにもうかつでした……。
残念ながら近くまで行くことはできませんでしたが、思い思いに飛び跳ねたり、小さいのを威嚇したりしている姿はなんともほほえましく、いつまでも眺めていたいと思ったのでした。
ムツゴロウは地域のシンボルマークにもなっていますし、また昨年小社で刊行した『佐賀読本』の編集にあたってもたくさんの写真を見ていたので、すっかり見たつもりになっていましたが、じつは私はそれまで本物のムツゴロウを見たことがありませんでした。そして、見たことがないというその事実に、はじめて気がついたのです。生まれは長崎、現在は佐賀、有明海にこれほど近い場所にいながら、いかにもうかつでした……。
残念ながら近くまで行くことはできませんでしたが、思い思いに飛び跳ねたり、小さいのを威嚇したりしている姿はなんともほほえましく、いつまでも眺めていたいと思ったのでした。
(A子)
2008年04月15日
枝吉神陽が会った人々5 安藤伯恕
弘化3年(1846)の旅のメンバーについて、前回もわからないという書き込みをしました。
今回もやはりよくわからない人物です。
宇和島の安藤伯恕。『枝吉神陽先生遺稿』に記された落款によると、「宇和島安藤知忠」とあることから、宇和島藩儒臣の安藤霞園という人ではないかと考えています。この人の父は安藤観生、字を伯容というらしく、そうではないかと想像しています。毎度のことながら、ご教示を待ちます。
当時の宇和島藩主は伊達宗城です。佐賀藩主鍋島直正とは従弟にあたり、関係も親密だったようです。家臣の間にも何か近しいような気持ちがはたらいたとも想像できます。
安藤伯恕が神陽に贈った詩。
鴉声鐘響暁沈々。唱罷驪歌涙湿襟。三四年間交友意。数千里外別離心。斜陽桑海雁行遠。落木蘇山秋気深。定識旅亭孤宿処。夢魂猶在茗渓潯。
送世徳枝吉君西帰。辱弟南豫安藤知忠拝。
今回もやはりよくわからない人物です。
宇和島の安藤伯恕。『枝吉神陽先生遺稿』に記された落款によると、「宇和島安藤知忠」とあることから、宇和島藩儒臣の安藤霞園という人ではないかと考えています。この人の父は安藤観生、字を伯容というらしく、そうではないかと想像しています。毎度のことながら、ご教示を待ちます。
当時の宇和島藩主は伊達宗城です。佐賀藩主鍋島直正とは従弟にあたり、関係も親密だったようです。家臣の間にも何か近しいような気持ちがはたらいたとも想像できます。
安藤伯恕が神陽に贈った詩。
鴉声鐘響暁沈々。唱罷驪歌涙湿襟。三四年間交友意。数千里外別離心。斜陽桑海雁行遠。落木蘇山秋気深。定識旅亭孤宿処。夢魂猶在茗渓潯。
送世徳枝吉君西帰。辱弟南豫安藤知忠拝。
2008年04月12日
展覧会にいってきました
今日は昼食で外出した足で久しぶりに佐賀県立美術館に出かけてみました。
現在、「平成19年度新収蔵品展」というコレクション展が行われており、書や絵画、伝統工芸品など初めて観るものも多く大変興味深い展覧会でした。
なかでも、興味を引かれたのは三代藩主鍋島綱茂の絵画です(テーマ展「孔子をみる」にもありました)。緻密に細い線まで描かれたその絵画は画家の作かと思うほど繊細に描かれており、佐賀藩主の幅広い教養の高さを思わされました。
また、副島種臣の書も新たに収蔵されており迫力の作品でした。
時間があまりなくゆっくり鑑賞することができませんでしたが、雨の休日にでも(雨でなくとも)もう一度でかけてみたいと思う展覧会でした。
博物館のほうではテーマ展の「孔子をみる――えがかれた聖人――」も開催中でした。
来週4月18日(金)は多久市の多久聖廟で春の「釈菜」も行われるようです。今年は多久聖廟創建300年にあたり、これを機に『論語』について見直してみるのもいいですね。
詳しくは、コレクション展「平成19年度新収蔵品展」「孔子をみる――えがかれた聖人――」。
現在、「平成19年度新収蔵品展」というコレクション展が行われており、書や絵画、伝統工芸品など初めて観るものも多く大変興味深い展覧会でした。
なかでも、興味を引かれたのは三代藩主鍋島綱茂の絵画です(テーマ展「孔子をみる」にもありました)。緻密に細い線まで描かれたその絵画は画家の作かと思うほど繊細に描かれており、佐賀藩主の幅広い教養の高さを思わされました。
また、副島種臣の書も新たに収蔵されており迫力の作品でした。
時間があまりなくゆっくり鑑賞することができませんでしたが、雨の休日にでも(雨でなくとも)もう一度でかけてみたいと思う展覧会でした。
博物館のほうではテーマ展の「孔子をみる――えがかれた聖人――」も開催中でした。
来週4月18日(金)は多久市の多久聖廟で春の「釈菜」も行われるようです。今年は多久聖廟創建300年にあたり、これを機に『論語』について見直してみるのもいいですね。
詳しくは、コレクション展「平成19年度新収蔵品展」「孔子をみる――えがかれた聖人――」。
(M)
2008年04月09日
編集見習い日記-その4-
今回は一冊の本をご紹介します。
外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫、1986)
タイトルに惹かれ手にとって眺めていると、編集長も若いころに読んだ本だというのですぐにその場で購入しました。しかし、この数ヶ月間一度もページを開かれることなく、自宅の本棚に眠っていた一冊です。
4月1日(火)付の朝日新聞に、この本の著者である外山氏のコラムが掲載され、ふと思い出して読み始めました。ぱらぱらとページをめくりながら、気になったところを少しずつ読んでいるだけですが、それだけでもずいぶん頭の中がすっきりした、というと、安直でしょうか。しかし実際、そんな気がするのです。
「忘却恐怖症」。コラムにはこのような言葉がありました。これについて、氏は前掲書の中で次のように述べておられます。
そして、このように結論づけられています。
最後にしっかりと釘を刺しておられる。さすがですね。まずは「しっかりとした価値観」を持つ。これがないと、いつも自分自身に振り回されてばかり、ということになりかねません。自分のよりどころとなるものを作っておかねばと思う今日この頃です。
外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫、1986)
タイトルに惹かれ手にとって眺めていると、編集長も若いころに読んだ本だというのですぐにその場で購入しました。しかし、この数ヶ月間一度もページを開かれることなく、自宅の本棚に眠っていた一冊です。
4月1日(火)付の朝日新聞に、この本の著者である外山氏のコラムが掲載され、ふと思い出して読み始めました。ぱらぱらとページをめくりながら、気になったところを少しずつ読んでいるだけですが、それだけでもずいぶん頭の中がすっきりした、というと、安直でしょうか。しかし実際、そんな気がするのです。
「忘却恐怖症」。コラムにはこのような言葉がありました。これについて、氏は前掲書の中で次のように述べておられます。
こどものときから、忘れてはいけない、忘れてはいけない、と教えられ、忘れたと言っては叱られてきた。そのせいもあって、忘れることに恐怖心をいだき続けている。(中略)倉庫としての頭にとっては、忘却は敵である。博識は学問のある証拠であった。(中略)どんどん摂取したら、どんどん排泄しないといけない。(中略)頭をよく働かせるには、この“忘れる”ことが、きわめて大切である。
そして、このように結論づけられています。
忘れるのは価値観にもとづいて忘れる。(中略)価値観がしっかりしていないと、大切なものを忘れ、つまらないものを覚えていることになる。これについては、さらに考えなくてはならない。
最後にしっかりと釘を刺しておられる。さすがですね。まずは「しっかりとした価値観」を持つ。これがないと、いつも自分自身に振り回されてばかり、ということになりかねません。自分のよりどころとなるものを作っておかねばと思う今日この頃です。
(A子)
2008年04月05日
枝吉神陽が会った人々4 十文字栗軒
前々回からの諸国遊行のメンバーの一人、十文字栗軒は経歴が詳しくわかりません。
「涌谷町の文化財/涌谷伊達家歴代の邑主」
(http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/wakuya/bunzai.pdf)
の中の⑮亘理胤元の項に、
……涌谷は十文字栗軒を中心として仙台藩の中でも勤王派として活躍した。……
とあるくらいしか、現在見つけられていません。
胤元によって甥の十文字秀雄とともに北海道に新天地を探索に遣わされたことが、
涌谷伊達家のHP
(http://members.jcom.home.ne.jp/2131535101/datetanemoto.html)
に記されています。
北海道立文書館編『十文字家文書』があるそうですが、未見です。
栗軒についてご存じの方ご教示下さい。
「涌谷町の文化財/涌谷伊達家歴代の邑主」
(http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/wakuya/bunzai.pdf)
の中の⑮亘理胤元の項に、
……涌谷は十文字栗軒を中心として仙台藩の中でも勤王派として活躍した。……
とあるくらいしか、現在見つけられていません。
胤元によって甥の十文字秀雄とともに北海道に新天地を探索に遣わされたことが、
涌谷伊達家のHP
(http://members.jcom.home.ne.jp/2131535101/datetanemoto.html)
に記されています。
北海道立文書館編『十文字家文書』があるそうですが、未見です。
栗軒についてご存じの方ご教示下さい。
2008年04月02日
意外な発見!
昨年9月に出門堂より発行した『佐賀読本』は県内にとどまらず県外からも多くの反響の声がありました。佐賀県のさまざまなことがらを時系列を軸にからめとってまとめ、今までにありそうでなかった一冊。歴史だけでなく産業や文化などがどのように伝わってきたか、生まれたのかをわかりやすく、しかも総ルビの、ついでに言えばいろんな仕事のネタにも使えそうなすぐれものです!
(私事ながら、結婚式の引出物にもしてしまいました。これが好評でした~!)
昨年12月4日付けの朝日新聞佐賀版にも記事が掲載されました。
――今年9月に出版したところ、佐賀市内の書店売り上げランキングで、6週にわたってベスト10入りするなど評判になっている。県も職員の研修でテキストに活用することを検討している。……8世紀に編集された肥前国風土記について解説した章では、佐賀と呼ばれるようになった言い伝えを紹介。地名の由来には、思わず「ほー」とうなずかされてしまう。また、徐福渡来伝説や葉隠など佐賀にゆかりのあるキーワードも解説。佐賀の温泉やお菓子も取りあげている。――
と紹介されています。
編集に携わった私も長年佐賀に住んでいるのに知らないことばかりで、新たな佐賀の魅力にひかれています。
この春、新社会人となる方々も『佐賀読本』で意外な発見があるかもしれませんよ。
そして……先週末、草森紳一さん(評論家)の訃報がとびこんできました。
草森さんは出門堂での出版の予定もたくさんあったのですが、わが編集長は仕事をこえてやりとりしており、草森さんにぞっこんでした。この報せを受けてからは日を追うごとにため息をくりかえしています。
心よりご冥福をお祈りします。
(私事ながら、結婚式の引出物にもしてしまいました。これが好評でした~!)
昨年12月4日付けの朝日新聞佐賀版にも記事が掲載されました。
――今年9月に出版したところ、佐賀市内の書店売り上げランキングで、6週にわたってベスト10入りするなど評判になっている。県も職員の研修でテキストに活用することを検討している。……8世紀に編集された肥前国風土記について解説した章では、佐賀と呼ばれるようになった言い伝えを紹介。地名の由来には、思わず「ほー」とうなずかされてしまう。また、徐福渡来伝説や葉隠など佐賀にゆかりのあるキーワードも解説。佐賀の温泉やお菓子も取りあげている。――
と紹介されています。
編集に携わった私も長年佐賀に住んでいるのに知らないことばかりで、新たな佐賀の魅力にひかれています。
この春、新社会人となる方々も『佐賀読本』で意外な発見があるかもしれませんよ。
そして……先週末、草森紳一さん(評論家)の訃報がとびこんできました。
草森さんは出門堂での出版の予定もたくさんあったのですが、わが編集長は仕事をこえてやりとりしており、草森さんにぞっこんでした。この報せを受けてからは日を追うごとにため息をくりかえしています。
心よりご冥福をお祈りします。
タグ :佐賀ガイドブック