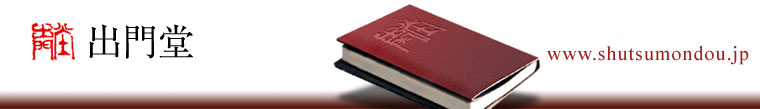佐賀の出版元 出門堂 | 編集見習い日記
2008年09月06日
「あ~れ~~」にも技術が要る?!
制作中の本の取材で、ある着付けの先生を訪ねたときのこと。
時代劇などで目にする、女性が着物の帯をほどかれる場面。実はそのシーンには着付けの技術が関係しているそうです。最近の着付け方法は様々な留め具を使用して何本もの紐でしばり、着崩れしないように保っているため、一度でほどくことはできないそうです。その先生の着付けは、一切それらの留め具を使用しません。ですので、帯をほどく時は「あ~れ~~」状態でとけるそうです。しかし、着崩れしにくいながらも圧迫感がないので長く着物を着ていられるそうです。本来の着物文化のうえではあたりまえのことだったのかもしれません。
何気なく見ていた時代劇にも日本の文化の巧みな技が隠されていたのですね。
ただし、女性が人前で帯をほどくのは貞節がないことを意味するため絶対にしないでほしいとおっしゃっていました。
時代劇などで目にする、女性が着物の帯をほどかれる場面。実はそのシーンには着付けの技術が関係しているそうです。最近の着付け方法は様々な留め具を使用して何本もの紐でしばり、着崩れしないように保っているため、一度でほどくことはできないそうです。その先生の着付けは、一切それらの留め具を使用しません。ですので、帯をほどく時は「あ~れ~~」状態でとけるそうです。しかし、着崩れしにくいながらも圧迫感がないので長く着物を着ていられるそうです。本来の着物文化のうえではあたりまえのことだったのかもしれません。
何気なく見ていた時代劇にも日本の文化の巧みな技が隠されていたのですね。
ただし、女性が人前で帯をほどくのは貞節がないことを意味するため絶対にしないでほしいとおっしゃっていました。
(M)
2008年06月26日
編集見習い日記-その7-
この仕事をするようになってから、他人が書いた手紙を読む機会が随分と増えました。著者の先生方や読者の皆様からいただく手紙、そして編集長からそうした方々に宛てる手紙などが主で、内容も形式もさまざまですがどれも味があり、書いた人の思いが手に取るように伝わってくるものばかりです。
私も書籍や書類を発送する際に手紙を書きますが、なかなか思うように書けず、もどかしい思いをすることがよくあります。簡単な用件を伝えるだけの手紙なのですが、そういうものほどかえって手間取ってしまい、その度に自分の言葉の引き出しがいかに少ないかということを実感させられます。
さて手紙といえば、平川祐弘著『米国大統領への手紙――市丸利之助伝』という本をご存じでしょうか? この本は、絶版となっていた新潮社版を増補改訂、出門堂のシリーズ「肥前佐賀文庫」の記念すべき第1冊目として2006年5月に刊行されました。
海軍航空部隊指揮官であった市丸利之助(唐津出身)は、硫黄島で玉砕する前に、時の米国大統領ルーズベルトへ宛てて日文・英文の遺書をのこしました。「ルーズベルトニ与フル書」と題されたその手紙は、激しい戦火をくぐり抜けていまも米国に現存しています。これほどまでに強い思いが込められた手紙を、私は今までに見たことがありません。
彼が遺した和歌約千首を収めた『市丸利之助歌集』とあわせて、ぜひご一読下さい。
私も書籍や書類を発送する際に手紙を書きますが、なかなか思うように書けず、もどかしい思いをすることがよくあります。簡単な用件を伝えるだけの手紙なのですが、そういうものほどかえって手間取ってしまい、その度に自分の言葉の引き出しがいかに少ないかということを実感させられます。
さて手紙といえば、平川祐弘著『米国大統領への手紙――市丸利之助伝』という本をご存じでしょうか? この本は、絶版となっていた新潮社版を増補改訂、出門堂のシリーズ「肥前佐賀文庫」の記念すべき第1冊目として2006年5月に刊行されました。
海軍航空部隊指揮官であった市丸利之助(唐津出身)は、硫黄島で玉砕する前に、時の米国大統領ルーズベルトへ宛てて日文・英文の遺書をのこしました。「ルーズベルトニ与フル書」と題されたその手紙は、激しい戦火をくぐり抜けていまも米国に現存しています。これほどまでに強い思いが込められた手紙を、私は今までに見たことがありません。
彼が遺した和歌約千首を収めた『市丸利之助歌集』とあわせて、ぜひご一読下さい。
2008年05月31日
編集見習い日記-その6-
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
出門堂に入門してはや一年、私が企画の段階から関わってきたはじめての本が、まもなく刊行されます。昨年、『佐賀読本』が書店に並んでいるのを見たときにもうれしさがこみ上げてきたのを覚えていますが、やはり一冊の本ができあがっていく過程をはじめからみてくると、一入の感慨があります。
このエッセイには、昭和のはじめ、佐賀市の本庄という小さな町に育った少女が出会った日々の出来事がつづられています。本書のいたるところにあふれる著者の思いは、同じ頃を生きた人々はもちろん、当時を知らない私たち若い世代にもしっかりと伝わってきます。
提灯を片手に暗い夜道をいっしょに歩いてくれた小父さんのこと、いまも心のひとすみにある父と「私」の「狸の薬局」のこと、少女の日常のひとつひとつに触れると、彼女自身や周りの大人たちのやさしいぬくもりに包まれるようです。希薄になってきたといわれる「大人」と「子供」のつながりが、昭和のはじめ、少女の周りにたしかにあったのだということがひしひしと感じられます。あたたかくて、なつかしくて、そして少しせつない36の掌篇です。
6月20日に発行予定の出門堂の新刊です。ご期待下さい。

著者 小山内富子
挿絵 緒方義彦
目次
なしてかの道
大人はしっきゃ親代わりたい
私が斜視だったころのことなど
寒稽古
メダカの御冥福
功名の雨傘
キャーモンの日
出直し喧嘩
戻り橋
もぐら打ち
徒らに机上の装飾とする勿れ
空を飛んだ鯛
村の巡査と一升の米
ぜんもんさんの宴
父の兄弟と古代オリンピック
狸の薬局
ホッテントットの化粧料
千人針と野菜爆弾
さんとく銀行
毬子を抱いて戻った友達
父の女装
色彩二題
鼈甲の煙草ケース
魚の哲学
文字のない墓石
遠い眺め
海辺のハイジ
方言賛歌
ピンクの雨
虚構であったとしても
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
乳母車
道を急ぐことはない
菩提寺の本堂で
窓のない蔵の窓
五文字の電報
出門堂に入門してはや一年、私が企画の段階から関わってきたはじめての本が、まもなく刊行されます。昨年、『佐賀読本』が書店に並んでいるのを見たときにもうれしさがこみ上げてきたのを覚えていますが、やはり一冊の本ができあがっていく過程をはじめからみてくると、一入の感慨があります。
このエッセイには、昭和のはじめ、佐賀市の本庄という小さな町に育った少女が出会った日々の出来事がつづられています。本書のいたるところにあふれる著者の思いは、同じ頃を生きた人々はもちろん、当時を知らない私たち若い世代にもしっかりと伝わってきます。
提灯を片手に暗い夜道をいっしょに歩いてくれた小父さんのこと、いまも心のひとすみにある父と「私」の「狸の薬局」のこと、少女の日常のひとつひとつに触れると、彼女自身や周りの大人たちのやさしいぬくもりに包まれるようです。希薄になってきたといわれる「大人」と「子供」のつながりが、昭和のはじめ、少女の周りにたしかにあったのだということがひしひしと感じられます。あたたかくて、なつかしくて、そして少しせつない36の掌篇です。
6月20日に発行予定の出門堂の新刊です。ご期待下さい。

著者 小山内富子
挿絵 緒方義彦
目次
なしてかの道
大人はしっきゃ親代わりたい
私が斜視だったころのことなど
寒稽古
メダカの御冥福
功名の雨傘
キャーモンの日
出直し喧嘩
戻り橋
もぐら打ち
徒らに机上の装飾とする勿れ
空を飛んだ鯛
村の巡査と一升の米
ぜんもんさんの宴
父の兄弟と古代オリンピック
狸の薬局
ホッテントットの化粧料
千人針と野菜爆弾
さんとく銀行
毬子を抱いて戻った友達
父の女装
色彩二題
鼈甲の煙草ケース
魚の哲学
文字のない墓石
遠い眺め
海辺のハイジ
方言賛歌
ピンクの雨
虚構であったとしても
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
乳母車
道を急ぐことはない
菩提寺の本堂で
窓のない蔵の窓
五文字の電報
(A子)
2008年04月21日
編集見習い日記-その5-
先週末の佐賀は良く晴れたので、太良町までドライブに行ってきました。佐賀県の西南部に位置する有明海に面した町で、車を降りると潮の香りがほんわりと漂ってきます。ちょうど潮が引いて、広大な干潟が広がっていました。見ると、干潟の上に動くものがあります。ムツゴロウです。それもものすごい数の。
ムツゴロウは地域のシンボルマークにもなっていますし、また昨年小社で刊行した『佐賀読本』の編集にあたってもたくさんの写真を見ていたので、すっかり見たつもりになっていましたが、じつは私はそれまで本物のムツゴロウを見たことがありませんでした。そして、見たことがないというその事実に、はじめて気がついたのです。生まれは長崎、現在は佐賀、有明海にこれほど近い場所にいながら、いかにもうかつでした……。
残念ながら近くまで行くことはできませんでしたが、思い思いに飛び跳ねたり、小さいのを威嚇したりしている姿はなんともほほえましく、いつまでも眺めていたいと思ったのでした。
ムツゴロウは地域のシンボルマークにもなっていますし、また昨年小社で刊行した『佐賀読本』の編集にあたってもたくさんの写真を見ていたので、すっかり見たつもりになっていましたが、じつは私はそれまで本物のムツゴロウを見たことがありませんでした。そして、見たことがないというその事実に、はじめて気がついたのです。生まれは長崎、現在は佐賀、有明海にこれほど近い場所にいながら、いかにもうかつでした……。
残念ながら近くまで行くことはできませんでしたが、思い思いに飛び跳ねたり、小さいのを威嚇したりしている姿はなんともほほえましく、いつまでも眺めていたいと思ったのでした。
(A子)
2008年04月09日
編集見習い日記-その4-
今回は一冊の本をご紹介します。
外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫、1986)
タイトルに惹かれ手にとって眺めていると、編集長も若いころに読んだ本だというのですぐにその場で購入しました。しかし、この数ヶ月間一度もページを開かれることなく、自宅の本棚に眠っていた一冊です。
4月1日(火)付の朝日新聞に、この本の著者である外山氏のコラムが掲載され、ふと思い出して読み始めました。ぱらぱらとページをめくりながら、気になったところを少しずつ読んでいるだけですが、それだけでもずいぶん頭の中がすっきりした、というと、安直でしょうか。しかし実際、そんな気がするのです。
「忘却恐怖症」。コラムにはこのような言葉がありました。これについて、氏は前掲書の中で次のように述べておられます。
そして、このように結論づけられています。
最後にしっかりと釘を刺しておられる。さすがですね。まずは「しっかりとした価値観」を持つ。これがないと、いつも自分自身に振り回されてばかり、ということになりかねません。自分のよりどころとなるものを作っておかねばと思う今日この頃です。
外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫、1986)
タイトルに惹かれ手にとって眺めていると、編集長も若いころに読んだ本だというのですぐにその場で購入しました。しかし、この数ヶ月間一度もページを開かれることなく、自宅の本棚に眠っていた一冊です。
4月1日(火)付の朝日新聞に、この本の著者である外山氏のコラムが掲載され、ふと思い出して読み始めました。ぱらぱらとページをめくりながら、気になったところを少しずつ読んでいるだけですが、それだけでもずいぶん頭の中がすっきりした、というと、安直でしょうか。しかし実際、そんな気がするのです。
「忘却恐怖症」。コラムにはこのような言葉がありました。これについて、氏は前掲書の中で次のように述べておられます。
こどものときから、忘れてはいけない、忘れてはいけない、と教えられ、忘れたと言っては叱られてきた。そのせいもあって、忘れることに恐怖心をいだき続けている。(中略)倉庫としての頭にとっては、忘却は敵である。博識は学問のある証拠であった。(中略)どんどん摂取したら、どんどん排泄しないといけない。(中略)頭をよく働かせるには、この“忘れる”ことが、きわめて大切である。
そして、このように結論づけられています。
忘れるのは価値観にもとづいて忘れる。(中略)価値観がしっかりしていないと、大切なものを忘れ、つまらないものを覚えていることになる。これについては、さらに考えなくてはならない。
最後にしっかりと釘を刺しておられる。さすがですね。まずは「しっかりとした価値観」を持つ。これがないと、いつも自分自身に振り回されてばかり、ということになりかねません。自分のよりどころとなるものを作っておかねばと思う今日この頃です。
(A子)
2008年03月28日
編集見習い日記-その3-
A子です。
先日、小城市にある中林梧竹記念館へ行ってきました。こぢんまりとした、大変シンプルな展示室ではありますが、一歩足を踏み入れると、そこには独特の、やさしく穏やかな空気が流れています。中林梧竹という人の人柄を肌に感じながら、作品をゆっくりと眺めることができます。
小学生のときに近所の書道教室に通い始めてから中学生まで、いわゆる「お習字」の経験はあるものの、「書」というもののなんたるか、まったく理解しておりません。ましてや他人の作品を見て分析をするほどの知識は皆無なのですが、ひとつ、見ていてはっとした作品がありました。
みなさんもよくご存知の「いろはにほへと」で始まる歌を書いたものですが、一目見ただけではあまり美しい字には見えません。ですが、それが展示されていた作品の中で私が最も心惹かれたものでありました。前に立ってぼんやりと眺めていたときに、ひと文字ひと文字がしだいに浮き上がって、そこからあぶり出しのように、原型となった漢字の姿が見えてきたのです。たとえば、「た」という字は「太」、「な」という字は「奈」といった具合です。ごくごく当たり前のことなのでしょうが、まるで数学の公式を見つけたかような、大発見をした気持ちになりました。
この出門堂で働いていなければ、「書」にたいしてそれほど興味を持つこともなく、おそらくこの先もずっと、こういったものの見え方はしなかったのではなかろうかと思います。編集見習いとなって約10ヶ月が経ちますが、最近になって少しずつ、この仕事の面白さを実感するようになってきました。
上記の作品は、出門堂が制作を担当しました「桜雲洞収蔵 中林梧竹書画」にも収録されていますので、ぜひご覧下さい。
先日、小城市にある中林梧竹記念館へ行ってきました。こぢんまりとした、大変シンプルな展示室ではありますが、一歩足を踏み入れると、そこには独特の、やさしく穏やかな空気が流れています。中林梧竹という人の人柄を肌に感じながら、作品をゆっくりと眺めることができます。
小学生のときに近所の書道教室に通い始めてから中学生まで、いわゆる「お習字」の経験はあるものの、「書」というもののなんたるか、まったく理解しておりません。ましてや他人の作品を見て分析をするほどの知識は皆無なのですが、ひとつ、見ていてはっとした作品がありました。
みなさんもよくご存知の「いろはにほへと」で始まる歌を書いたものですが、一目見ただけではあまり美しい字には見えません。ですが、それが展示されていた作品の中で私が最も心惹かれたものでありました。前に立ってぼんやりと眺めていたときに、ひと文字ひと文字がしだいに浮き上がって、そこからあぶり出しのように、原型となった漢字の姿が見えてきたのです。たとえば、「た」という字は「太」、「な」という字は「奈」といった具合です。ごくごく当たり前のことなのでしょうが、まるで数学の公式を見つけたかような、大発見をした気持ちになりました。
この出門堂で働いていなければ、「書」にたいしてそれほど興味を持つこともなく、おそらくこの先もずっと、こういったものの見え方はしなかったのではなかろうかと思います。編集見習いとなって約10ヶ月が経ちますが、最近になって少しずつ、この仕事の面白さを実感するようになってきました。
上記の作品は、出門堂が制作を担当しました「桜雲洞収蔵 中林梧竹書画」にも収録されていますので、ぜひご覧下さい。
タグ :中林梧竹
2008年03月24日
編集見習い日記-その2-
こんにちは、A子です。
ここ出門堂では、毎日たくさんの話をします。歴史のことであったり、今朝の新聞記事についてであったり、あるいは昨晩観たお笑い番組のことであったり、その内容は実にさまざまですが、小さな出来事でもそこから何かを読み取り、議論を膨らませていくのが我らが編集長の得意とするところです。
私が特に気に入っているのは、文字や言葉についての話です。先日、お客様と私の電話でのやり取りを聞いていた編集長から、「きみはよく『さようでございます』って言うよね」との指摘を受けました。確かに、私はよくお客様に対して「さようでございます」という言い方をします。なんだかサムライのようですが、そもそもこの「さよう」とは、どういう意味を持つのでしょうか。
参考までに、『新明解 国語辞典』第四版(三省堂)により、以下に要点をまとめてみました。
さよう【然様】
一、「その通り・そのよう」の意の丁寧語。
二、相手の言った事や自分の思い出した事を肯定する気持を表わす。「そうです」の老人語。「左様」とも書く。
また、『新潮国語辞典』第二版(新潮社)には、
さヨウ【左様・然様】(「左」はあて字)
一、そのとおり。そう。
二、相手のことばを肯定したり、なにか思いあたったりした時にいうことば。そう。そうだ。
とあります。現在使っている「さようなら」も、「それでは、また逢う日までお元気に」という意味で、やはり「然様(さよう)」という言葉からきているようです。
こうして言葉のもとを辿り、その言葉ができた背景や歴史に触れてみると、これまであまり意識することもなく使っていた言葉が、少し違った響きを帯びて聞こえてきます。人と会話をしたり、頭の中でものを考えたり、私たちは毎日何かしら「言葉」に関わって生活しています。めまぐるしく変わっていく現代社会の中で、言葉も変化を余儀なくされることがあると思います。けれども、毎日使うものだからこそ、時には少し立ち止まって、「言葉」というものにじっくり向き合ってみることも必要なのかなと思った一日でした。
ここ出門堂では、毎日たくさんの話をします。歴史のことであったり、今朝の新聞記事についてであったり、あるいは昨晩観たお笑い番組のことであったり、その内容は実にさまざまですが、小さな出来事でもそこから何かを読み取り、議論を膨らませていくのが我らが編集長の得意とするところです。
私が特に気に入っているのは、文字や言葉についての話です。先日、お客様と私の電話でのやり取りを聞いていた編集長から、「きみはよく『さようでございます』って言うよね」との指摘を受けました。確かに、私はよくお客様に対して「さようでございます」という言い方をします。なんだかサムライのようですが、そもそもこの「さよう」とは、どういう意味を持つのでしょうか。
参考までに、『新明解 国語辞典』第四版(三省堂)により、以下に要点をまとめてみました。
さよう【然様】
一、「その通り・そのよう」の意の丁寧語。
二、相手の言った事や自分の思い出した事を肯定する気持を表わす。「そうです」の老人語。「左様」とも書く。
また、『新潮国語辞典』第二版(新潮社)には、
さヨウ【左様・然様】(「左」はあて字)
一、そのとおり。そう。
二、相手のことばを肯定したり、なにか思いあたったりした時にいうことば。そう。そうだ。
とあります。現在使っている「さようなら」も、「それでは、また逢う日までお元気に」という意味で、やはり「然様(さよう)」という言葉からきているようです。
こうして言葉のもとを辿り、その言葉ができた背景や歴史に触れてみると、これまであまり意識することもなく使っていた言葉が、少し違った響きを帯びて聞こえてきます。人と会話をしたり、頭の中でものを考えたり、私たちは毎日何かしら「言葉」に関わって生活しています。めまぐるしく変わっていく現代社会の中で、言葉も変化を余儀なくされることがあると思います。けれども、毎日使うものだからこそ、時には少し立ち止まって、「言葉」というものにじっくり向き合ってみることも必要なのかなと思った一日でした。
2008年03月17日
編集見習い日記-その1-
はじめまして、編集見習いのA子です。
全く縁がないと思っていたこの土地にひょんな事から越して来たのが一年前。何とか働き口を見つけたものの、この仕事の大変なこと。悪戦苦闘の連続ですが、編集修業の毎日の中で見聞きしたこと、考えたこと、感じたことをお伝えしていきたいと思います。
さて、私が佐賀に来て最初に思ったことの一つに、「『はがくれ』とはなんぞや」ということがあります。街のいたる所に「はがくれ」の文字を見るものの、それが何を意味するのか皆目見当がつかず、まるで外国にでも来たかのような感覚を覚えました。それが、ここ「出門堂」に入門してから、ははー、なるほど!と思いました。
ちょうどその頃、『老いと死の超克―わが葉隠』という本が出門堂から刊行されたのですが、この時に初めて「はがくれ」=「は」+「がくれ」=「葉」+「隠」だと知ったのです。
そんな状態ですから、佐賀の郷土本を出している出門堂の編集者が果たして務まるのかと不安になられる方もおられるでしょうが、私これから一所懸命やって参ります。どうか今後ともよろしくお付き合い下さいませ。
全く縁がないと思っていたこの土地にひょんな事から越して来たのが一年前。何とか働き口を見つけたものの、この仕事の大変なこと。悪戦苦闘の連続ですが、編集修業の毎日の中で見聞きしたこと、考えたこと、感じたことをお伝えしていきたいと思います。
さて、私が佐賀に来て最初に思ったことの一つに、「『はがくれ』とはなんぞや」ということがあります。街のいたる所に「はがくれ」の文字を見るものの、それが何を意味するのか皆目見当がつかず、まるで外国にでも来たかのような感覚を覚えました。それが、ここ「出門堂」に入門してから、ははー、なるほど!と思いました。
ちょうどその頃、『老いと死の超克―わが葉隠』という本が出門堂から刊行されたのですが、この時に初めて「はがくれ」=「は」+「がくれ」=「葉」+「隠」だと知ったのです。
そんな状態ですから、佐賀の郷土本を出している出門堂の編集者が果たして務まるのかと不安になられる方もおられるでしょうが、私これから一所懸命やって参ります。どうか今後ともよろしくお付き合い下さいませ。
タグ :葉隠