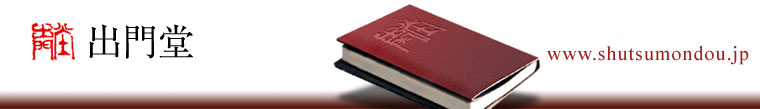佐賀の出版元 出門堂 | 枝吉神陽が出会った人々
2008年06月02日
枝吉神陽が会った人々7 玉蟲拙斎
弘化3年(1846)4月15日に枝吉神陽一行が玉蟲拙斎の家に泊まったことが『十文字家文書』にあるそうです。
函館の山形道文先生(函館漢詩文化会会長)が北海道新聞に5回にわたるインタビュー構成で、堀利煕を中心に「堀奉行と箱館の侍たち」という記事が掲載され、その第4回目(2008年3月27日)に玉蟲拙斎について語っておられます。山形先生の了解を得て紹介いたします。
箱館八景扇面図の侍はあと二人。姫路藩出身の菅野潔は、昌平坂学問所の塾長に抜てきされるほどの秀才で、蝦夷地の紀行文「北遊乗」を記しました。扇面図では、七重村(現七飯町)周辺の風景を漢詩「七重晴嵐」として詠んでいます。
菅野は、箱館奉行の堀利煕が「誠終舎」と命名し、開設した庶民教育施設「心学講釈所」で孟子を講義しました。菅野は扇面図の侍の中で最初に江戸に帰ります。しかし、江戸には安政五年(一八五八年)から翌年にかけ、大老井伊直弼による政治弾圧「安政の大獄」の嵐が吹き荒れ、「国許永蟄居」の厳罰を受けたのです。
扇面図の最後の一人、仙台藩出身の玉虫左太夫は、後の戊辰戦争の末に非業の死を遂げる侍です。漢詩「山背帰帆」では、山背泊(現函館漁港)の風景を詠んでいます。
海湾縈曲擁牛山
山上模糊雲半間
尤愛漁村斜日景
千颿一送捲波還
「海は湾曲して臥牛山を抱き、山上はかすみ雲間に見え隠れする。何より素晴らしいのは山背泊漁村の夕暮れの風景。多くの船が一斉に波をけたてて港に戻ってくる」
玉虫も、昌平坂学問所の塾長を務め、諸藩の大名まで教えた人物。安政四年(一八五七年)、堀の近習役として蝦夷地の探索に付き従いました。玉虫の紀行文「入北記」には、扇面図の侍をはじめ、島義勇、松浦武四郎、榎本武揚らと交友したことが記されています。
万延元年(一八六〇年)一月、外国奉行を兼務していた堀の推挙で、日米修好通商条約批准書交換で米国に向かう使節団の一員に選ばれ、米国軍艦ポーハタン号で太平洋を渡ります。首都ワシントンで大統領ブキャナンに接見した後、アフリカ各地や香港に立ち寄りながら九ヵ月後に帰国。堀への報告書として世界一周の見聞記「航米日録」にまとめました。
巡察参加も海外渡航も堀の後押しによるもの。堀は玉虫の才能を愛し、将来の活躍を期待していたことでしょう。
時は流れ、大政奉還の後に江戸幕府は瓦解。戊辰戦争で薩摩藩、長州藩を中心とした新政府軍が北上する中、玉虫は東北、北陸の三十一藩による奥羽越列藩同盟の軍事局副頭取として戦い、敗れます。旧幕府軍の艦隊を率い「蝦夷共和国」建設を目指す同士、榎本武揚との合流を果たせず抗戦の首謀者として捕らえられました。
そして玉虫は明治二年(一八六九年)四月、牢前切腹を命じられ、首を落とされます。親交の深かった福沢諭吉は「福翁自伝」で、政府の戦後処理について「久我大納言を勅使に下向させたが、あろうことかあるまいことか仙台藩士が生首を七つ持ってきた」と玉虫の最期の様子を描き、早過ぎる死を嘆きました。
共に蝦夷地を巡察した榎本は明治政府に重用され、後に外務大臣、農商務大臣などを歴任します。もし、玉虫が戦禍を生き永らえ、蝦夷地に渡っていたら・・・。
と述べておられます。玉蟲は神陽の従弟・島義勇にも接触したことがわかります。
巻頭で上げておられる菅野白華は、このブログ「枝吉神陽が会った人々2」で紹介しました。ブログの公開1日後にインタビューが掲載されているのは偶然です。もちろん私のは孫引きですからいっしょにしてはいけませんが……。山形先生のような方がこうした人物を丹念に調査しておられることに敬意を表します。
函館の山形道文先生(函館漢詩文化会会長)が北海道新聞に5回にわたるインタビュー構成で、堀利煕を中心に「堀奉行と箱館の侍たち」という記事が掲載され、その第4回目(2008年3月27日)に玉蟲拙斎について語っておられます。山形先生の了解を得て紹介いたします。
箱館八景扇面図の侍はあと二人。姫路藩出身の菅野潔は、昌平坂学問所の塾長に抜てきされるほどの秀才で、蝦夷地の紀行文「北遊乗」を記しました。扇面図では、七重村(現七飯町)周辺の風景を漢詩「七重晴嵐」として詠んでいます。
菅野は、箱館奉行の堀利煕が「誠終舎」と命名し、開設した庶民教育施設「心学講釈所」で孟子を講義しました。菅野は扇面図の侍の中で最初に江戸に帰ります。しかし、江戸には安政五年(一八五八年)から翌年にかけ、大老井伊直弼による政治弾圧「安政の大獄」の嵐が吹き荒れ、「国許永蟄居」の厳罰を受けたのです。
扇面図の最後の一人、仙台藩出身の玉虫左太夫は、後の戊辰戦争の末に非業の死を遂げる侍です。漢詩「山背帰帆」では、山背泊(現函館漁港)の風景を詠んでいます。
海湾縈曲擁牛山
山上模糊雲半間
尤愛漁村斜日景
千颿一送捲波還
「海は湾曲して臥牛山を抱き、山上はかすみ雲間に見え隠れする。何より素晴らしいのは山背泊漁村の夕暮れの風景。多くの船が一斉に波をけたてて港に戻ってくる」
玉虫も、昌平坂学問所の塾長を務め、諸藩の大名まで教えた人物。安政四年(一八五七年)、堀の近習役として蝦夷地の探索に付き従いました。玉虫の紀行文「入北記」には、扇面図の侍をはじめ、島義勇、松浦武四郎、榎本武揚らと交友したことが記されています。
万延元年(一八六〇年)一月、外国奉行を兼務していた堀の推挙で、日米修好通商条約批准書交換で米国に向かう使節団の一員に選ばれ、米国軍艦ポーハタン号で太平洋を渡ります。首都ワシントンで大統領ブキャナンに接見した後、アフリカ各地や香港に立ち寄りながら九ヵ月後に帰国。堀への報告書として世界一周の見聞記「航米日録」にまとめました。
巡察参加も海外渡航も堀の後押しによるもの。堀は玉虫の才能を愛し、将来の活躍を期待していたことでしょう。
時は流れ、大政奉還の後に江戸幕府は瓦解。戊辰戦争で薩摩藩、長州藩を中心とした新政府軍が北上する中、玉虫は東北、北陸の三十一藩による奥羽越列藩同盟の軍事局副頭取として戦い、敗れます。旧幕府軍の艦隊を率い「蝦夷共和国」建設を目指す同士、榎本武揚との合流を果たせず抗戦の首謀者として捕らえられました。
そして玉虫は明治二年(一八六九年)四月、牢前切腹を命じられ、首を落とされます。親交の深かった福沢諭吉は「福翁自伝」で、政府の戦後処理について「久我大納言を勅使に下向させたが、あろうことかあるまいことか仙台藩士が生首を七つ持ってきた」と玉虫の最期の様子を描き、早過ぎる死を嘆きました。
共に蝦夷地を巡察した榎本は明治政府に重用され、後に外務大臣、農商務大臣などを歴任します。もし、玉虫が戦禍を生き永らえ、蝦夷地に渡っていたら・・・。
と述べておられます。玉蟲は神陽の従弟・島義勇にも接触したことがわかります。
巻頭で上げておられる菅野白華は、このブログ「枝吉神陽が会った人々2」で紹介しました。ブログの公開1日後にインタビューが掲載されているのは偶然です。もちろん私のは孫引きですからいっしょにしてはいけませんが……。山形先生のような方がこうした人物を丹念に調査しておられることに敬意を表します。
2008年05月04日
枝吉神陽が会った人々6 五十嵐三省
3回目に取り上げた藤森弘庵ともに五十嵐三省とも、この旅の中で交遊しています。弘化3年(1846)3月頃と思われます。
さて、この五十嵐三省ですが、「五十嵐三省墓誌」なるものがあり、『事実文編』七六に収録されています。撰文は木原元礼です。それによると、
文政2年(1819)~明治7年(1874)。名を儀一、別号を愛山。常陸土浦の人。土屋氏に仕える。木原とともに藤森弘庵のもとで学んだ。昌平坂学問所にも留学した。
ということがわかります。このような人物たちがどの程度顕彰されているのか?
常陽新聞新社『民話一○○話 土浦ものがたり』の中に取り上げられているようですが未読です。
神陽の足取りを追ってみると、昌平坂学問所の人物が藩をこえて交際が密であったことがよくわかります。
さて、この五十嵐三省ですが、「五十嵐三省墓誌」なるものがあり、『事実文編』七六に収録されています。撰文は木原元礼です。それによると、
文政2年(1819)~明治7年(1874)。名を儀一、別号を愛山。常陸土浦の人。土屋氏に仕える。木原とともに藤森弘庵のもとで学んだ。昌平坂学問所にも留学した。
ということがわかります。このような人物たちがどの程度顕彰されているのか?
常陽新聞新社『民話一○○話 土浦ものがたり』の中に取り上げられているようですが未読です。
神陽の足取りを追ってみると、昌平坂学問所の人物が藩をこえて交際が密であったことがよくわかります。
2008年04月15日
枝吉神陽が会った人々5 安藤伯恕
弘化3年(1846)の旅のメンバーについて、前回もわからないという書き込みをしました。
今回もやはりよくわからない人物です。
宇和島の安藤伯恕。『枝吉神陽先生遺稿』に記された落款によると、「宇和島安藤知忠」とあることから、宇和島藩儒臣の安藤霞園という人ではないかと考えています。この人の父は安藤観生、字を伯容というらしく、そうではないかと想像しています。毎度のことながら、ご教示を待ちます。
当時の宇和島藩主は伊達宗城です。佐賀藩主鍋島直正とは従弟にあたり、関係も親密だったようです。家臣の間にも何か近しいような気持ちがはたらいたとも想像できます。
安藤伯恕が神陽に贈った詩。
鴉声鐘響暁沈々。唱罷驪歌涙湿襟。三四年間交友意。数千里外別離心。斜陽桑海雁行遠。落木蘇山秋気深。定識旅亭孤宿処。夢魂猶在茗渓潯。
送世徳枝吉君西帰。辱弟南豫安藤知忠拝。
今回もやはりよくわからない人物です。
宇和島の安藤伯恕。『枝吉神陽先生遺稿』に記された落款によると、「宇和島安藤知忠」とあることから、宇和島藩儒臣の安藤霞園という人ではないかと考えています。この人の父は安藤観生、字を伯容というらしく、そうではないかと想像しています。毎度のことながら、ご教示を待ちます。
当時の宇和島藩主は伊達宗城です。佐賀藩主鍋島直正とは従弟にあたり、関係も親密だったようです。家臣の間にも何か近しいような気持ちがはたらいたとも想像できます。
安藤伯恕が神陽に贈った詩。
鴉声鐘響暁沈々。唱罷驪歌涙湿襟。三四年間交友意。数千里外別離心。斜陽桑海雁行遠。落木蘇山秋気深。定識旅亭孤宿処。夢魂猶在茗渓潯。
送世徳枝吉君西帰。辱弟南豫安藤知忠拝。
2008年04月05日
枝吉神陽が会った人々4 十文字栗軒
前々回からの諸国遊行のメンバーの一人、十文字栗軒は経歴が詳しくわかりません。
「涌谷町の文化財/涌谷伊達家歴代の邑主」
(http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/wakuya/bunzai.pdf)
の中の⑮亘理胤元の項に、
……涌谷は十文字栗軒を中心として仙台藩の中でも勤王派として活躍した。……
とあるくらいしか、現在見つけられていません。
胤元によって甥の十文字秀雄とともに北海道に新天地を探索に遣わされたことが、
涌谷伊達家のHP
(http://members.jcom.home.ne.jp/2131535101/datetanemoto.html)
に記されています。
北海道立文書館編『十文字家文書』があるそうですが、未見です。
栗軒についてご存じの方ご教示下さい。
「涌谷町の文化財/涌谷伊達家歴代の邑主」
(http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/wakuya/bunzai.pdf)
の中の⑮亘理胤元の項に、
……涌谷は十文字栗軒を中心として仙台藩の中でも勤王派として活躍した。……
とあるくらいしか、現在見つけられていません。
胤元によって甥の十文字秀雄とともに北海道に新天地を探索に遣わされたことが、
涌谷伊達家のHP
(http://members.jcom.home.ne.jp/2131535101/datetanemoto.html)
に記されています。
北海道立文書館編『十文字家文書』があるそうですが、未見です。
栗軒についてご存じの方ご教示下さい。
2008年03月31日
枝吉神陽が会った人々3 藤森弘庵
前回同様に『枝吉神陽先生遺稿』をたよりに神陽の交友を追うと、弘化3年(1846)3月、土浦藩の藩校郁文館の客分になり、藤森弘庵と詩文の応酬をしていることが記されています。
郁文館は、寛政11(1799)年に土浦藩の藩校として創設され、当時は藤森をはじめ教授陣が充実し、全国でも著名であったようです。
藤森弘安は、明治にむけて多くの人物を育てた功績は大きいといえるでしょう。明徳出版社からは『梁川星巌・藤森弘庵』として伝記も出ています。
神陽の出身である肥前佐賀藩の関わりでいえば、藤森は古賀穀堂(第1回の古賀侗庵の兄で、鍋島直正の師傅)や古賀侗庵に師事したということもあり、神陽とのあいだには共通の話題も少なくなかったろうと思われます。25歳の神陽は、藤田東湖らとならんで名を馳せていた藤森弘庵(47歳)と詩を交わす機会を得たのです。
神陽にむけた藤森の詩を、『枝吉神陽先生遺稿』から紹介します。
明月投窮巷。光輝生茅茨。諸君海内俊。文彩擅英奇。
湖海元龍気。兼以絶世姿。晤言起慵懦。傾蓋獲心知。
相逢如昨日。又此告別離。雄藩星宿分。各在天一陲。
男児四方志。再会非難期。会期雖非難。亦抱別離悲。
今日分手後。慵懦誰能医。
奉送別枝吉十文字安藤木村諸先生。
藤森連再拝。
郁文館は、寛政11(1799)年に土浦藩の藩校として創設され、当時は藤森をはじめ教授陣が充実し、全国でも著名であったようです。
藤森弘安は、明治にむけて多くの人物を育てた功績は大きいといえるでしょう。明徳出版社からは『梁川星巌・藤森弘庵』として伝記も出ています。
神陽の出身である肥前佐賀藩の関わりでいえば、藤森は古賀穀堂(第1回の古賀侗庵の兄で、鍋島直正の師傅)や古賀侗庵に師事したということもあり、神陽とのあいだには共通の話題も少なくなかったろうと思われます。25歳の神陽は、藤田東湖らとならんで名を馳せていた藤森弘庵(47歳)と詩を交わす機会を得たのです。
神陽にむけた藤森の詩を、『枝吉神陽先生遺稿』から紹介します。
明月投窮巷。光輝生茅茨。諸君海内俊。文彩擅英奇。
湖海元龍気。兼以絶世姿。晤言起慵懦。傾蓋獲心知。
相逢如昨日。又此告別離。雄藩星宿分。各在天一陲。
男児四方志。再会非難期。会期雖非難。亦抱別離悲。
今日分手後。慵懦誰能医。
奉送別枝吉十文字安藤木村諸先生。
藤森連再拝。
2008年03月26日
枝吉神陽が会った人々2 菅野白華
『枝吉神陽先生遺稿』楠神社・枝吉神陽関係年譜(江頭慶宣氏作成)には、神陽が弘化3年(1846)3月9日に鎌倉・水戸・房総・奥羽・越後など諸国へ向けて旅に出たことが記されています。そのときに同行したメンバーの一人に、菅野白華がいます。
菅野白華については、『「昌平黌」物語』(斯文会、1973)によると、
白華、名は潔、字は聖與、狷介と称した。播磨の人、昌平黌に入り、業を古賀侗庵に受け、姫路藩に仕え、江戸藩邸の教授に補せられたが、安政戊午の大獄に嫌疑を以て下獄し、ついで姫路に拘せられた。文久三年赦にあい好古堂の副督学に補せられた。明治三年三月八日歿、年五十一。
とあります。神陽と同じく古賀侗庵の門人ということです。『枝吉神陽先生遺稿』には、己酉(1849年)に江戸を去る神陽の送別として送った菅野白華の詩が収められています。日本各地から江戸へ留学した秀才たちの交友があったことがうかがえます。
萬里江関隔月帰。知君長鋏有餘煇。西溟他日屠鯨手。且向江湖試一揮。
己酉春。送世徳枝吉大兄帰火国。賦之叙別。兄帰途将游上国。潔。菅野氏白華。
菅野白華については、『「昌平黌」物語』(斯文会、1973)によると、
白華、名は潔、字は聖與、狷介と称した。播磨の人、昌平黌に入り、業を古賀侗庵に受け、姫路藩に仕え、江戸藩邸の教授に補せられたが、安政戊午の大獄に嫌疑を以て下獄し、ついで姫路に拘せられた。文久三年赦にあい好古堂の副督学に補せられた。明治三年三月八日歿、年五十一。
とあります。神陽と同じく古賀侗庵の門人ということです。『枝吉神陽先生遺稿』には、己酉(1849年)に江戸を去る神陽の送別として送った菅野白華の詩が収められています。日本各地から江戸へ留学した秀才たちの交友があったことがうかがえます。
萬里江関隔月帰。知君長鋏有餘煇。西溟他日屠鯨手。且向江湖試一揮。
己酉春。送世徳枝吉大兄帰火国。賦之叙別。兄帰途将游上国。潔。菅野氏白華。
2008年03月19日
枝吉神陽が会った人々1 古賀侗庵
枝吉神陽が会った人々
枝吉神陽は幕末佐賀藩勤王運動の首魁です。神陽と出会った当時の名士たちは、現在かならずしも著名ではありません。しかし、顕彰されるに足りない人物たちかといえば、まったくそうではありません。
まずは、枝吉神陽が天保15年9月10日に昌平坂学問書書生寮に入寮したころ以降の交友の痕跡を小社刊『枝吉神陽先生遺稿』(龍造寺八幡宮楠神社編)を参考に追ってみます。
まず、第1番目は、古賀侗庵です。
「丁未九日」という神陽の詩の注に、「甲辰重陽。陪侗庵先生。牟田口先生。于桜田藩邸。……」とあります。甲辰つまり天保15年(1884)の重陽(9月9日)に古賀侗庵にしたがって桜田藩邸を訪れているということです。神陽23歳、古賀侗庵はこのとき57歳です。
『佐賀県歴史人名事典』(洋学堂書店、1993復刻)によると、
名は煜、通称は小太郎、侗菴と号す。古賀精里の第三子なり。天明八年を以て生る。寛政年間父精里選ばれて幕府に仕ふるや、之に従って江戸に赴く。刻苦勉励学大に揚る。文化六年擢んでられて儒官となり、父子駢番同じく学政を董す。世以て異数となす。弘化四年病を以て終る。享年六十。
とあります。古賀精里ですら現在知る人が少ないのは残念です。さらに知られていない侗庵は、さまざまな面で父精里を遥かに凌ぐ江戸時代を代表する知識人で、幕末維新を考える上で、もっと注目される必要がある人物だと思います。ペリーが来航する半世紀も前に幕府の中枢で開国論をとなえたことも、この父子の注目すべき点です。詳しくは、この春小社より刊行予定の肥前佐賀文庫003をお待ちください。
枝吉神陽は幕末佐賀藩勤王運動の首魁です。神陽と出会った当時の名士たちは、現在かならずしも著名ではありません。しかし、顕彰されるに足りない人物たちかといえば、まったくそうではありません。
まずは、枝吉神陽が天保15年9月10日に昌平坂学問書書生寮に入寮したころ以降の交友の痕跡を小社刊『枝吉神陽先生遺稿』(龍造寺八幡宮楠神社編)を参考に追ってみます。
まず、第1番目は、古賀侗庵です。
「丁未九日」という神陽の詩の注に、「甲辰重陽。陪侗庵先生。牟田口先生。于桜田藩邸。……」とあります。甲辰つまり天保15年(1884)の重陽(9月9日)に古賀侗庵にしたがって桜田藩邸を訪れているということです。神陽23歳、古賀侗庵はこのとき57歳です。
『佐賀県歴史人名事典』(洋学堂書店、1993復刻)によると、
名は煜、通称は小太郎、侗菴と号す。古賀精里の第三子なり。天明八年を以て生る。寛政年間父精里選ばれて幕府に仕ふるや、之に従って江戸に赴く。刻苦勉励学大に揚る。文化六年擢んでられて儒官となり、父子駢番同じく学政を董す。世以て異数となす。弘化四年病を以て終る。享年六十。
とあります。古賀精里ですら現在知る人が少ないのは残念です。さらに知られていない侗庵は、さまざまな面で父精里を遥かに凌ぐ江戸時代を代表する知識人で、幕末維新を考える上で、もっと注目される必要がある人物だと思います。ペリーが来航する半世紀も前に幕府の中枢で開国論をとなえたことも、この父子の注目すべき点です。詳しくは、この春小社より刊行予定の肥前佐賀文庫003をお待ちください。