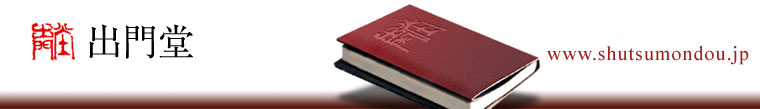佐賀の出版元 出門堂 | 今日のおすすめ
2008年12月08日
西郷隆盛と副島種臣
小松帯刀についての紹介が意外にも好評で、薩摩を中心とした幕末維新に対する関心の高さを感じます。そこで小松帯刀につづいて、西郷隆盛や大久保利通と佐賀についてのエピソードをひとつ紹介します。
以下は、副島種臣の西郷についての回想から。
大久保利通がさまざまな面で副島種臣を頼りにしたことは有名ですが、征韓論争以降は西郷と交遊が深かったことがわかる談話です。南洲墓地にある鹿児島改葬碑が副島の揮毫であることは、こうした副島と西郷隆盛(南洲)との関係によるものだと思われます。大久保と西郷、時期によりこの二人が頼りにしたのが副島種臣でした。
幕末維新に活躍したのは薩摩ばかりではありません。薩長土肥の肥前、つまり佐賀の視点から描かれた幕末維新のわかりやすいガイドとして、大変好評の一冊、福岡博著『佐賀の幕末維新 八賢伝』出門堂をぜひご一読ください。(X)
以下は、副島種臣の西郷についての回想から。
初まりは説の合うこともあり、合わぬこともあっただろうがね。あの人の死に至る時、拙者に遺言をされたで。死ぬ三日前に西郷に仕えて居った、薩摩の岡部と云う者に、「最早や自分は討死をするから出で行け」と云うて、それを出さるる時に、「副島が支那から帰って逢えたならば、謹んで死するなかれ」と言われた。その趣意を考えるに重もに荒いことを最早するなと言われたと見ゆるて。それが最後の遺言であった。その岡部と鈴木某と二人連れで遺言を通じた。これは全く征韓の頃から外の朋友を離れ、拙者とは時々手紙の往復もし、それも人の往来位で、薩摩人の往来で、委托して物言うたことも沢山ある。その頃からその遺言を拙者の為めに発するに至られたと見ゆるて。およそ役人と云う者はどんな朋友でも、説の合う時と合わぬ時とあるものだ。その時はやはり争論をする。もっとも征韓論までは拙者は大久保とが一番懇意にあったようにある。ただ征韓の一条だけが、彼と見込の違ったと云うもので。そこで、役人の懇意は、あるいは討論、あるいは異論と云うことは往々ある。ある度毎に見解の衝突は言うまでもない話だ。
(島善高編『副島種臣全集2』慧文社より〔全体を新字新仮名づかいに、一部の漢字表記の接続詞を平仮名に修正して紹介しました)
大久保利通がさまざまな面で副島種臣を頼りにしたことは有名ですが、征韓論争以降は西郷と交遊が深かったことがわかる談話です。南洲墓地にある鹿児島改葬碑が副島の揮毫であることは、こうした副島と西郷隆盛(南洲)との関係によるものだと思われます。大久保と西郷、時期によりこの二人が頼りにしたのが副島種臣でした。
幕末維新に活躍したのは薩摩ばかりではありません。薩長土肥の肥前、つまり佐賀の視点から描かれた幕末維新のわかりやすいガイドとして、大変好評の一冊、福岡博著『佐賀の幕末維新 八賢伝』出門堂をぜひご一読ください。(X)
2008年11月20日
「よみかき論語」を出版します
この11月末に「よみかき論語」を出版します。
以下、その内容を紹介します。
「よみ」「かき」「そろばん」は、かつての日本で不可欠の基本的な素養とされていました。
本書は、「よみ」と「かき」を一冊で同時に学ぶ本格的で簡便な「論語テキスト」です。
「よみ」とは「論語の素読」に代表されます。
訓読体を声に出して諳誦することにより、たくさんの言葉や、美しい文章の基礎、
そして倫理観や人生観をも学ぶ目的で、「よみ」は重視されたのです。
「かき」とは手習い、つまり習字のことです。
毛筆で文字をおぼえながら、筆づかいや文字の美しさを身につけました。
かなも漢字も毛筆で書くことを前提にできているため、書写は私たちの
すべての美意識の原点ともいえるのです。
間もなく出門堂のサイトで詳しく紹介します。
以下、その内容を紹介します。
「よみ」「かき」「そろばん」は、かつての日本で不可欠の基本的な素養とされていました。
本書は、「よみ」と「かき」を一冊で同時に学ぶ本格的で簡便な「論語テキスト」です。
「よみ」とは「論語の素読」に代表されます。
訓読体を声に出して諳誦することにより、たくさんの言葉や、美しい文章の基礎、
そして倫理観や人生観をも学ぶ目的で、「よみ」は重視されたのです。
「かき」とは手習い、つまり習字のことです。
毛筆で文字をおぼえながら、筆づかいや文字の美しさを身につけました。
かなも漢字も毛筆で書くことを前提にできているため、書写は私たちの
すべての美意識の原点ともいえるのです。
間もなく出門堂のサイトで詳しく紹介します。
2008年09月05日
イトモロコ(佐賀の淡水魚)
イトモロコ。
あまり大きくならないようで、写真のものも5㎝ぐらいです。
いつも水槽の下の方にいて、
他の種類とちがって、
餌を求めて水面に浮上する動きはほとんど見せません。
背中に黒い模様があるので、すぐにイトモロコと知れます。
からだの流線型が最も美しいと思っています。

(X)
あまり大きくならないようで、写真のものも5㎝ぐらいです。
いつも水槽の下の方にいて、
他の種類とちがって、
餌を求めて水面に浮上する動きはほとんど見せません。
背中に黒い模様があるので、すぐにイトモロコと知れます。
からだの流線型が最も美しいと思っています。

(X)
2008年09月02日
オイカワの雄
オイカワの雄。
オイカワを食した感想は、「うまい」「まずい」と両極を耳にします。
私も10㎝弱のオイカワを天ぷらにしたことがありますが、
けっこうおいしく食べました。
雄は繁殖期になると縞模様が青みを増し、
ひれの先に赤い色がさし、
大変派手な姿になります。
もっと大きく雄壮な雄を獲ったことがありますが、
いずれもすごいジャンプ力で、
バケツから川へ帰っていきました。

(X)
オイカワを食した感想は、「うまい」「まずい」と両極を耳にします。
私も10㎝弱のオイカワを天ぷらにしたことがありますが、
けっこうおいしく食べました。
雄は繁殖期になると縞模様が青みを増し、
ひれの先に赤い色がさし、
大変派手な姿になります。
もっと大きく雄壮な雄を獲ったことがありますが、
いずれもすごいジャンプ力で、
バケツから川へ帰っていきました。

(X)
2008年08月13日
帰省
この時期、ふるさとで過ごす人も多いことと思います。佐賀へ帰省される方へ読んでいただきたい一冊をご紹介します。
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿 小山内富子著
なつかしい佐賀の風景とともに、昭和初期の人々のつながりとあたたかさが満載です。
ところで、この美味しい魚は何だったんでしょうね?
出門堂の本は佐賀県内の書店でも販売しています。
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿 小山内富子著
なつかしい佐賀の風景とともに、昭和初期の人々のつながりとあたたかさが満載です。
―― 「魚の哲学」より ――つつましく、そしてたくましく生きていた昔の人から学ぶことは多いです。
「昔ゃない、我がん家の川端に魚のどっさい泳ぎよっとば見つくっきい、竿竹ば持ってきて、飯(めし)盗人(ぬすっと)、早(は)よあっち行けちゅうて、魚ば追っ払いよったちゅうばい。……」
「なし、魚の飯盗人ね」
「魚ば菜(しゃあ)に飯ば食(た)ぶっき、美味(うま)か魚につられて、飯ばどっさい食(く)うてしまうけんたい」
「そんない、ご飯の代わりに魚ばどっさい食べたらよかやんね。魚は栄養価も高っかし、堀から、只で取りゆもん。……」
「栄養はあっばってん、魚ばっかいじゃあ、働く体力はできんたい。それにない、人間、贅沢な味ば知ってしまうぎ、もとにゃ戻りにくかたい。第一、只で手に入っとも、労働者にとっちゃ禍(わざわい)の種(たね)たい。只の味ば覚えてしまうぎ、働くとが阿呆らしゅうなって、勤労意欲の削(そ)がるっちゅーてない。そいが、家の切り盛りば受け持っ姑婆ちゃんたちの生活哲学じゃったったい」
ところで、この美味しい魚は何だったんでしょうね?
出門堂の本は佐賀県内の書店でも販売しています。
(M)
2008年07月24日
支え合うことの大切さ(佐賀新聞)
7月20日付の佐賀新聞「マイブック」のコーナーで『おもやいどがしこでん』(古賀悦子著)がとりあげられました。佐賀大学に通う白石恵里さんは、
と、自身がまわりの人たちに支えられてきた経験を振り返ります。
また、
と、これからへ向けた力強い思いが語られています。
神埼ライオンズクラブ40周年記念出版『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読下さい。
進路や作品制作で悩むことはあったけど、先輩の励ましや、先生の後押しを受け、美協展で一席を取ることができた。
と、自身がまわりの人たちに支えられてきた経験を振り返ります。
また、
自分では表現できない鮮やかな色使い、独自の世界観に引かれこの絵本を手に取った。・・・・・・支え合うことの大切さと人への思いやり。この絵本のテーマを忘れず、見る人から喜んでもらえる作品をつくり続けたい。
と、これからへ向けた力強い思いが語られています。
神埼ライオンズクラブ40周年記念出版『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読下さい。
(A子)
2008年07月23日
人と人とのつながり
7月19日付、佐賀新聞に小社出版の小山内富子著『「にゃーごとあろう」父の後ろ姿』について掲載されました。見出しは「失われた大事なもの」とされていました。
私たちが知らないうちに手放してしまったものがみえてくるような一冊です。佐賀という地域と人のあたたかさがたくさん詰まった上質のエッセイが心地よい涙をさそいます。

昭和初期の佐賀市の農村を背景に、小山内さんと実父とのやりとりや、今でも忘れられない言葉などが温かな文体でつづられている。……今回出版したエッセーは、戦前の佐賀を舞台に、現代では忘れかけた人と人との交流などが随所にちりばめられている。……小山内さんは「著名人でもない父のことを書くのはちゅうちょしたが、父の言葉、佐賀の自然は今の私の心の中の色彩となっている。失われた大事なものを集めるつもりで書いた」と話す。
私たちが知らないうちに手放してしまったものがみえてくるような一冊です。佐賀という地域と人のあたたかさがたくさん詰まった上質のエッセイが心地よい涙をさそいます。
(M)

2008年07月15日
「おもやい」精神養って(佐賀新聞)
佐賀新聞(2008年7月9日)に「40周年でオリジナル絵本 神埼ライオンズクラブ」という記事が掲載されました。
神埼市の神埼ライオンズクラブ(吉原俊樹会長)が40周年記念事業の取り組みとしてオリジナルの絵本「おもやい どがしこでん」を作製した。自然の恵みをみんなで共有する物語で、3000冊を印刷、市内の小学校や幼稚園、保育園に贈呈する。
と、この本の制作の背景が紹介されています。また、
読者は4歳児から小学低学年が対象で、「おもやい」精神をテーマにした。「どがしこでん」という何でも独り占めしようとする生き物が、自然などを共有することの大切さを学ぶという内容になっている。
と評されています。
付け加えますが、他方では、
「これは、大人のための絵本では?」(「佐賀・神埼・吉野ヶ里だより」)
http://shi113113k.sagafan.jp/e32236.html
というコメントもいただいています。
たいへんうれしいことです。
記事の末尾は、
吉原会長は「分かち合うことの大切さを学ぶ作品。親と子の対話のきっかけとなれば」と話す。
と締めくくられています。
『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読を。
神埼市の神埼ライオンズクラブ(吉原俊樹会長)が40周年記念事業の取り組みとしてオリジナルの絵本「おもやい どがしこでん」を作製した。自然の恵みをみんなで共有する物語で、3000冊を印刷、市内の小学校や幼稚園、保育園に贈呈する。
と、この本の制作の背景が紹介されています。また、
読者は4歳児から小学低学年が対象で、「おもやい」精神をテーマにした。「どがしこでん」という何でも独り占めしようとする生き物が、自然などを共有することの大切さを学ぶという内容になっている。
と評されています。
付け加えますが、他方では、
「これは、大人のための絵本では?」(「佐賀・神埼・吉野ヶ里だより」)
http://shi113113k.sagafan.jp/e32236.html
というコメントもいただいています。
たいへんうれしいことです。
記事の末尾は、
吉原会長は「分かち合うことの大切さを学ぶ作品。親と子の対話のきっかけとなれば」と話す。
と締めくくられています。
『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読を。
(A子)
2008年07月02日
おもやいの気持ち
6月30日付佐賀新聞の有明抄に小社出版の絵本『おもやいどがしこでん』について記事が掲載されました。一部をご紹介します。
「もやう」という方言は「共同して使う」の意味。……語源は「舫う」から来ている。船と船をつないだり、船を杭につないだりすることだ。……人と人の付き合いの中で「分かち合う」「一緒に使う」の意味に変えた昔の人の感性はすばらしい。個人主義が横行し、ふれあいが不足している現代こそ、もういちど「もやう」ことで思いやりや親近感が生まれてくる
そして、神埼ライオンズクラブ40周年を記念して出版されたこの絵本に対して
……神埼の地名は「神幸(かみさき)」を由来とするとの説もある。古来から神と深いつながりがあったのだろう。絵本のタッチも原初のエネルギーにあふれている。
昔から続く「おもやい」のやさしい気持ちを今の子供たちにも繋げていきたいものです。
「もやう」という方言は「共同して使う」の意味。……語源は「舫う」から来ている。船と船をつないだり、船を杭につないだりすることだ。……人と人の付き合いの中で「分かち合う」「一緒に使う」の意味に変えた昔の人の感性はすばらしい。個人主義が横行し、ふれあいが不足している現代こそ、もういちど「もやう」ことで思いやりや親近感が生まれてくる
そして、神埼ライオンズクラブ40周年を記念して出版されたこの絵本に対して
……神埼の地名は「神幸(かみさき)」を由来とするとの説もある。古来から神と深いつながりがあったのだろう。絵本のタッチも原初のエネルギーにあふれている。
昔から続く「おもやい」のやさしい気持ちを今の子供たちにも繋げていきたいものです。
(M)
2008年06月06日
☆新刊のお知らせです☆
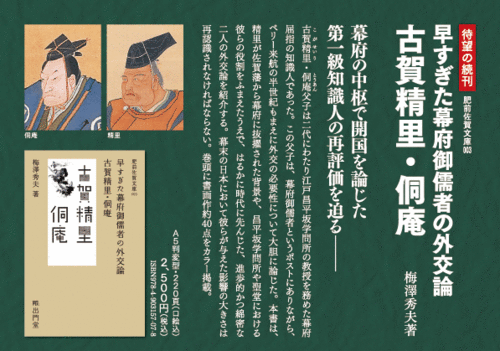 出門堂の待望のシリーズ「肥前佐賀文庫」の第3弾、
出門堂の待望のシリーズ「肥前佐賀文庫」の第3弾、肥前佐賀文庫003 早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵
がまもなく発刊となります。
6月20日発行予定です。
古賀精里は佐賀藩校弘道館の初代校長となり、のちに昌平坂学問所(昌平黌)という幕府の学校の教授となる異例の経歴を辿りました。
息子の侗庵は父精里と共に佐賀から江戸に移り、同じく昌平黌の教授となりました。
親子二代で昌平黌の先生という例はほかにはなかったようです。
現在の学校の教科書にはページの隅に「(注)」でしか取り上げられていない精里・侗庵親子ですが、彼らが幕府の中枢にありながら、ペリーが浦賀にやって来る半世紀も前に進歩的で綿密な外交論を唱えていたことが本書には紹介されています。彼らの先進的な考え方が幕末の日本にどれだけ大きな影響をあたえたか、再認識されるべきだと思います。
巻頭には二人の書画など約40点をカラー掲載している贅沢な一冊です。
刊行までもうしばらくお待ち下さい。
(M)
2008年04月12日
展覧会にいってきました
今日は昼食で外出した足で久しぶりに佐賀県立美術館に出かけてみました。
現在、「平成19年度新収蔵品展」というコレクション展が行われており、書や絵画、伝統工芸品など初めて観るものも多く大変興味深い展覧会でした。
なかでも、興味を引かれたのは三代藩主鍋島綱茂の絵画です(テーマ展「孔子をみる」にもありました)。緻密に細い線まで描かれたその絵画は画家の作かと思うほど繊細に描かれており、佐賀藩主の幅広い教養の高さを思わされました。
また、副島種臣の書も新たに収蔵されており迫力の作品でした。
時間があまりなくゆっくり鑑賞することができませんでしたが、雨の休日にでも(雨でなくとも)もう一度でかけてみたいと思う展覧会でした。
博物館のほうではテーマ展の「孔子をみる――えがかれた聖人――」も開催中でした。
来週4月18日(金)は多久市の多久聖廟で春の「釈菜」も行われるようです。今年は多久聖廟創建300年にあたり、これを機に『論語』について見直してみるのもいいですね。
詳しくは、コレクション展「平成19年度新収蔵品展」「孔子をみる――えがかれた聖人――」。
現在、「平成19年度新収蔵品展」というコレクション展が行われており、書や絵画、伝統工芸品など初めて観るものも多く大変興味深い展覧会でした。
なかでも、興味を引かれたのは三代藩主鍋島綱茂の絵画です(テーマ展「孔子をみる」にもありました)。緻密に細い線まで描かれたその絵画は画家の作かと思うほど繊細に描かれており、佐賀藩主の幅広い教養の高さを思わされました。
また、副島種臣の書も新たに収蔵されており迫力の作品でした。
時間があまりなくゆっくり鑑賞することができませんでしたが、雨の休日にでも(雨でなくとも)もう一度でかけてみたいと思う展覧会でした。
博物館のほうではテーマ展の「孔子をみる――えがかれた聖人――」も開催中でした。
来週4月18日(金)は多久市の多久聖廟で春の「釈菜」も行われるようです。今年は多久聖廟創建300年にあたり、これを機に『論語』について見直してみるのもいいですね。
詳しくは、コレクション展「平成19年度新収蔵品展」「孔子をみる――えがかれた聖人――」。
(M)