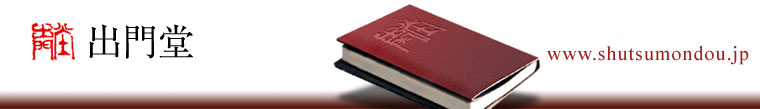佐賀の出版元 出門堂 | 2008年07月
2008年07月29日
楢林宗建によるわが国初の牛痘接種の実施日が特定される
小社『わが国はじめての牛痘種痘』の著者である深瀬泰旦先生から、お手紙をいただきました。その中で、楢林宗建の日本はじめての接種日を特定するにあたり、一定以上の信憑性をもった報告があるとされています。深瀬先生のご諒解を得て、以下紹介いたします。
ということです。この接種の後、全国各地の蘭医を中心にいっきに牛痘接種が広がっていきます。
なお、日本最初の種痘についてはさまざまな説があるようです。『わが国はじめての牛痘種痘』では、「楢林宗建が嘉永二年におこなった牛痘接種は、その成功が今日にいたる牛痘接種に継続しているという事実によって、本邦初の牛痘接種といってよいであろう」としめくくられています。
天然痘という、当時の驚異であった病の根絶のために苦心した多くの人々に敬意を表します。(X)
ピッツバーク大学名誉教授(歴史学)アン・ジャネッタさんの著書*によりますと、1849年8月14日の「蘭館日記」に
近頃バタビアからもたらされた牛痘物質をもちいて、今日モーニッケが3人の日本の子どもに接種した。長崎奉行はモーニッケから指導をうけるために、若い日本人医師に毎日出島に通うことを許可した。
との記事があるとのことです。8月14日を旧暦になおしますと(嘉永2年)6月26日にあたります。ジャネッタさんもこの日を接種日としています。
また建三郎の年齢ですが、さきの著書でも5ヶ月児(呉秀三)、10ヶ月児(「楢林家系譜」)、15ヶ月児(古賀十二郎)などいろいろな説があるとしてしまいましたが、孫にあたる楢林基成氏によりますと**、祖父建三郎の大正元年12月18日に撮影した写真に「63歳9ヶ月」と書かれているとのことですので、これから逆算すると「嘉永2年3月生まれ」になると断定しています。嘉永2年生まれであることは間違いありませんが、誕生日は何月何日かが不明ですので、この逆算がすぐに正しいとはいえないとおもいます――この点につきましてはさらなる考察が必要かと存じます――ので、「3ヶ月乃至4ヶ月の乳児」といっておいた方がよろしかろうと思っています。
*Ann Jannetta: The Vaccinators Smallpox, Medical Knowledge, and the Opening of Japan. Stanford University Press. Stanford, California 2007〔132ページ〕
**楢林基成『八十路坂』2007年〔18ページ〕
ということです。この接種の後、全国各地の蘭医を中心にいっきに牛痘接種が広がっていきます。
なお、日本最初の種痘についてはさまざまな説があるようです。『わが国はじめての牛痘種痘』では、「楢林宗建が嘉永二年におこなった牛痘接種は、その成功が今日にいたる牛痘接種に継続しているという事実によって、本邦初の牛痘接種といってよいであろう」としめくくられています。
天然痘という、当時の驚異であった病の根絶のために苦心した多くの人々に敬意を表します。(X)
2008年07月28日
肥前佐賀文庫003 古賀精里・侗庵が佐賀新聞有明抄に
7月28日の佐賀新聞「有明抄」で梅澤秀夫著『早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵』(出門堂)が取り上げられました。
ことし第一陣となる北方領土墓参団から話が起こされています。そして、
と紹介されています。また、
と述べられています。
なぜいま、古賀精里・侗庵父子について出版すべきなのか、という小社の企図の一端を代弁していただいたようにさえ思えました。(X)
ことし第一陣となる北方領土墓参団から話が起こされています。そして、
江戸時代、この北方領土へのロシアの脅威にどう対処するかを幕府に進言したのが、佐賀出身の朱子学者古賀精里・侗庵親子だった。清泉女子大学教授梅澤秀夫さんが書いた「早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵」(出門堂)を読むと、二人の先見性がよく分かる。
と紹介されています。また、
十八世紀末から十九世紀初頭にかけて、ロシアはシベリアを征服し、カムチャッカ半島から千島列島へ南下。レザノフが長崎に来て開港を迫った。精里はロシアの要求に対する想定問答集を作っている。それは和親と威嚇を両にらみした、知略に富んだものだった。
何が何でも外国人を実力排斥しようとする感情論が高まる中、冷静で合理的なものの見方をした古賀親子の存在をあらためて見直したい。
と述べられています。
なぜいま、古賀精里・侗庵父子について出版すべきなのか、という小社の企図の一端を代弁していただいたようにさえ思えました。(X)
2008年07月24日
支え合うことの大切さ(佐賀新聞)
7月20日付の佐賀新聞「マイブック」のコーナーで『おもやいどがしこでん』(古賀悦子著)がとりあげられました。佐賀大学に通う白石恵里さんは、
と、自身がまわりの人たちに支えられてきた経験を振り返ります。
また、
と、これからへ向けた力強い思いが語られています。
神埼ライオンズクラブ40周年記念出版『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読下さい。
進路や作品制作で悩むことはあったけど、先輩の励ましや、先生の後押しを受け、美協展で一席を取ることができた。
と、自身がまわりの人たちに支えられてきた経験を振り返ります。
また、
自分では表現できない鮮やかな色使い、独自の世界観に引かれこの絵本を手に取った。・・・・・・支え合うことの大切さと人への思いやり。この絵本のテーマを忘れず、見る人から喜んでもらえる作品をつくり続けたい。
と、これからへ向けた力強い思いが語られています。
神埼ライオンズクラブ40周年記念出版『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読下さい。
(A子)
2008年07月23日
人と人とのつながり
7月19日付、佐賀新聞に小社出版の小山内富子著『「にゃーごとあろう」父の後ろ姿』について掲載されました。見出しは「失われた大事なもの」とされていました。
私たちが知らないうちに手放してしまったものがみえてくるような一冊です。佐賀という地域と人のあたたかさがたくさん詰まった上質のエッセイが心地よい涙をさそいます。

昭和初期の佐賀市の農村を背景に、小山内さんと実父とのやりとりや、今でも忘れられない言葉などが温かな文体でつづられている。……今回出版したエッセーは、戦前の佐賀を舞台に、現代では忘れかけた人と人との交流などが随所にちりばめられている。……小山内さんは「著名人でもない父のことを書くのはちゅうちょしたが、父の言葉、佐賀の自然は今の私の心の中の色彩となっている。失われた大事なものを集めるつもりで書いた」と話す。
私たちが知らないうちに手放してしまったものがみえてくるような一冊です。佐賀という地域と人のあたたかさがたくさん詰まった上質のエッセイが心地よい涙をさそいます。
(M)

2008年07月15日
「おもやい」精神養って(佐賀新聞)
佐賀新聞(2008年7月9日)に「40周年でオリジナル絵本 神埼ライオンズクラブ」という記事が掲載されました。
神埼市の神埼ライオンズクラブ(吉原俊樹会長)が40周年記念事業の取り組みとしてオリジナルの絵本「おもやい どがしこでん」を作製した。自然の恵みをみんなで共有する物語で、3000冊を印刷、市内の小学校や幼稚園、保育園に贈呈する。
と、この本の制作の背景が紹介されています。また、
読者は4歳児から小学低学年が対象で、「おもやい」精神をテーマにした。「どがしこでん」という何でも独り占めしようとする生き物が、自然などを共有することの大切さを学ぶという内容になっている。
と評されています。
付け加えますが、他方では、
「これは、大人のための絵本では?」(「佐賀・神埼・吉野ヶ里だより」)
http://shi113113k.sagafan.jp/e32236.html
というコメントもいただいています。
たいへんうれしいことです。
記事の末尾は、
吉原会長は「分かち合うことの大切さを学ぶ作品。親と子の対話のきっかけとなれば」と話す。
と締めくくられています。
『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読を。
神埼市の神埼ライオンズクラブ(吉原俊樹会長)が40周年記念事業の取り組みとしてオリジナルの絵本「おもやい どがしこでん」を作製した。自然の恵みをみんなで共有する物語で、3000冊を印刷、市内の小学校や幼稚園、保育園に贈呈する。
と、この本の制作の背景が紹介されています。また、
読者は4歳児から小学低学年が対象で、「おもやい」精神をテーマにした。「どがしこでん」という何でも独り占めしようとする生き物が、自然などを共有することの大切さを学ぶという内容になっている。
と評されています。
付け加えますが、他方では、
「これは、大人のための絵本では?」(「佐賀・神埼・吉野ヶ里だより」)
http://shi113113k.sagafan.jp/e32236.html
というコメントもいただいています。
たいへんうれしいことです。
記事の末尾は、
吉原会長は「分かち合うことの大切さを学ぶ作品。親と子の対話のきっかけとなれば」と話す。
と締めくくられています。
『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読を。
(A子)
2008年07月08日
「子供は大人が思うとっほど柔(ヤワ)やなか」
小山内富子著『「にゃーごとあろう」父の後ろ姿』の中には、すてきな言葉がたくさんあります。そのうちの一つ、少女の父親が持論としていたものです。
子供にゃ難しかけんちうて漢字ば教えんたあ、間違うとったい。教えられんやった子にとっちゃ、習いそこない損になる。子供は大人が思うとっほど柔やなか
(同書「ピンクの雨」より)
昭和初期の父の言葉を、娘の回想によって記された本です。
易しいものがもてはやされる昨今、深く考えさせられるひとことです。
子供にゃ難しかけんちうて漢字ば教えんたあ、間違うとったい。教えられんやった子にとっちゃ、習いそこない損になる。子供は大人が思うとっほど柔やなか
(同書「ピンクの雨」より)
昭和初期の父の言葉を、娘の回想によって記された本です。
易しいものがもてはやされる昨今、深く考えさせられるひとことです。
(A子)
2008年07月03日
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
小社新刊
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
について、読者からたくさんお電話をいだいています。
このようなことは小社でもはじめてです。
寄せられた感想に共通しているのは、
一気によんでしまった
むかしがなつかしい
むかしの大人は立派だった
のような言葉ですが、昨日いただいたのは、
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
というものでした。
版元としてうれしいかぎりです。
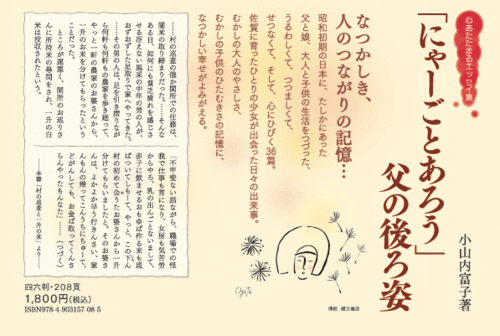
(X)
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
について、読者からたくさんお電話をいだいています。
このようなことは小社でもはじめてです。
寄せられた感想に共通しているのは、
一気によんでしまった
むかしがなつかしい
むかしの大人は立派だった
のような言葉ですが、昨日いただいたのは、
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
というものでした。
版元としてうれしいかぎりです。
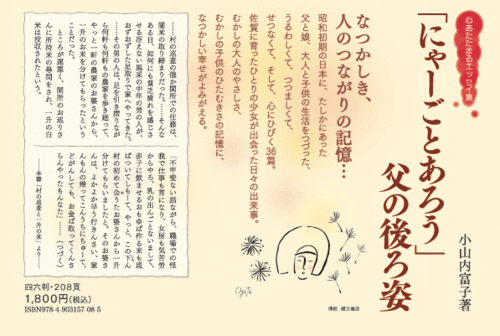
(X)
2008年07月02日
おもやいの気持ち
6月30日付佐賀新聞の有明抄に小社出版の絵本『おもやいどがしこでん』について記事が掲載されました。一部をご紹介します。
「もやう」という方言は「共同して使う」の意味。……語源は「舫う」から来ている。船と船をつないだり、船を杭につないだりすることだ。……人と人の付き合いの中で「分かち合う」「一緒に使う」の意味に変えた昔の人の感性はすばらしい。個人主義が横行し、ふれあいが不足している現代こそ、もういちど「もやう」ことで思いやりや親近感が生まれてくる
そして、神埼ライオンズクラブ40周年を記念して出版されたこの絵本に対して
……神埼の地名は「神幸(かみさき)」を由来とするとの説もある。古来から神と深いつながりがあったのだろう。絵本のタッチも原初のエネルギーにあふれている。
昔から続く「おもやい」のやさしい気持ちを今の子供たちにも繋げていきたいものです。
「もやう」という方言は「共同して使う」の意味。……語源は「舫う」から来ている。船と船をつないだり、船を杭につないだりすることだ。……人と人の付き合いの中で「分かち合う」「一緒に使う」の意味に変えた昔の人の感性はすばらしい。個人主義が横行し、ふれあいが不足している現代こそ、もういちど「もやう」ことで思いやりや親近感が生まれてくる
そして、神埼ライオンズクラブ40周年を記念して出版されたこの絵本に対して
……神埼の地名は「神幸(かみさき)」を由来とするとの説もある。古来から神と深いつながりがあったのだろう。絵本のタッチも原初のエネルギーにあふれている。
昔から続く「おもやい」のやさしい気持ちを今の子供たちにも繋げていきたいものです。
(M)