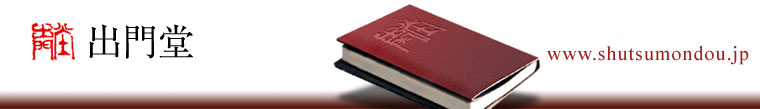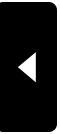佐賀の出版元 出門堂
2008年07月23日
人と人とのつながり
昭和初期の佐賀市の農村を背景に、小山内さんと実父とのやりとりや、今でも忘れられない言葉などが温かな文体でつづられている。……今回出版したエッセーは、戦前の佐賀を舞台に、現代では忘れかけた人と人との交流などが随所にちりばめられている。……小山内さんは「著名人でもない父のことを書くのはちゅうちょしたが、父の言葉、佐賀の自然は今の私の心の中の色彩となっている。失われた大事なものを集めるつもりで書いた」と話す。
私たちが知らないうちに手放してしまったものがみえてくるような一冊です。佐賀という地域と人のあたたかさがたくさん詰まった上質のエッセイが心地よい涙をさそいます。

Posted by 出門堂 at 13:36 | Comments(0) | 今日のおすすめ
2008年07月15日
「おもやい」精神養って(佐賀新聞)
神埼市の神埼ライオンズクラブ(吉原俊樹会長)が40周年記念事業の取り組みとしてオリジナルの絵本「おもやい どがしこでん」を作製した。自然の恵みをみんなで共有する物語で、3000冊を印刷、市内の小学校や幼稚園、保育園に贈呈する。
と、この本の制作の背景が紹介されています。また、
読者は4歳児から小学低学年が対象で、「おもやい」精神をテーマにした。「どがしこでん」という何でも独り占めしようとする生き物が、自然などを共有することの大切さを学ぶという内容になっている。
と評されています。
付け加えますが、他方では、
「これは、大人のための絵本では?」(「佐賀・神埼・吉野ヶ里だより」)
http://shi113113k.sagafan.jp/e32236.html
というコメントもいただいています。
たいへんうれしいことです。
記事の末尾は、
吉原会長は「分かち合うことの大切さを学ぶ作品。親と子の対話のきっかけとなれば」と話す。
と締めくくられています。
『おもやいどがしこでん』、ぜひご一読を。
Posted by 出門堂 at 12:11 | Comments(0) | 今日のおすすめ
2008年07月08日
「子供は大人が思うとっほど柔(ヤワ)やなか」
子供にゃ難しかけんちうて漢字ば教えんたあ、間違うとったい。教えられんやった子にとっちゃ、習いそこない損になる。子供は大人が思うとっほど柔やなか
(同書「ピンクの雨」より)
昭和初期の父の言葉を、娘の回想によって記された本です。
易しいものがもてはやされる昨今、深く考えさせられるひとことです。
Posted by 出門堂 at 10:08 | Comments(0) | 今日のひとこと
2008年07月03日
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
について、読者からたくさんお電話をいだいています。
このようなことは小社でもはじめてです。
寄せられた感想に共通しているのは、
一気によんでしまった
むかしがなつかしい
むかしの大人は立派だった
のような言葉ですが、昨日いただいたのは、
ひさしぶりにエッセイを読んで涙しました
というものでした。
版元としてうれしいかぎりです。
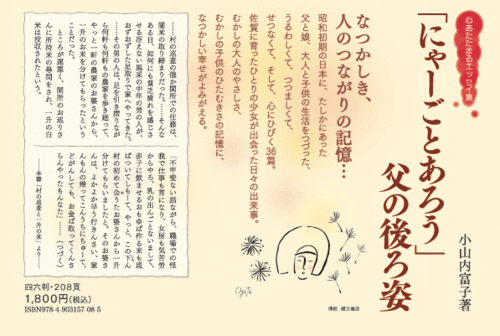
(X)
Posted by 出門堂 at 12:30 | Comments(0) | 今日のひとこと
2008年07月02日
おもやいの気持ち
「もやう」という方言は「共同して使う」の意味。……語源は「舫う」から来ている。船と船をつないだり、船を杭につないだりすることだ。……人と人の付き合いの中で「分かち合う」「一緒に使う」の意味に変えた昔の人の感性はすばらしい。個人主義が横行し、ふれあいが不足している現代こそ、もういちど「もやう」ことで思いやりや親近感が生まれてくる
そして、神埼ライオンズクラブ40周年を記念して出版されたこの絵本に対して
……神埼の地名は「神幸(かみさき)」を由来とするとの説もある。古来から神と深いつながりがあったのだろう。絵本のタッチも原初のエネルギーにあふれている。
昔から続く「おもやい」のやさしい気持ちを今の子供たちにも繋げていきたいものです。
Posted by 出門堂 at 11:06 | Comments(0) | 今日のおすすめ
2008年06月26日
編集見習い日記-その7-
私も書籍や書類を発送する際に手紙を書きますが、なかなか思うように書けず、もどかしい思いをすることがよくあります。簡単な用件を伝えるだけの手紙なのですが、そういうものほどかえって手間取ってしまい、その度に自分の言葉の引き出しがいかに少ないかということを実感させられます。
さて手紙といえば、平川祐弘著『米国大統領への手紙――市丸利之助伝』という本をご存じでしょうか? この本は、絶版となっていた新潮社版を増補改訂、出門堂のシリーズ「肥前佐賀文庫」の記念すべき第1冊目として2006年5月に刊行されました。
海軍航空部隊指揮官であった市丸利之助(唐津出身)は、硫黄島で玉砕する前に、時の米国大統領ルーズベルトへ宛てて日文・英文の遺書をのこしました。「ルーズベルトニ与フル書」と題されたその手紙は、激しい戦火をくぐり抜けていまも米国に現存しています。これほどまでに強い思いが込められた手紙を、私は今までに見たことがありません。
彼が遺した和歌約千首を収めた『市丸利之助歌集』とあわせて、ぜひご一読下さい。
Posted by 出門堂 at 11:02 | Comments(0) | 編集見習い日記
2008年06月14日
物部神社
いまは人気(ひとけ)もなくひっそりとした神社ですが、
金子信二『佐賀読本』では、『肥前国風土記』にある「物部経津主神」(もののべふつぬしのかみ)が祀られているといわれている神社です。

(X)
Posted by 出門堂 at 14:00 | Comments(0) | 取材日記
2008年06月12日
麦秋
スケールを枠に写しこむ技術がありませんが、掲載します。

(H)
Posted by 出門堂 at 09:20 | Comments(0) | 取材日記
2008年06月06日
☆新刊のお知らせです☆
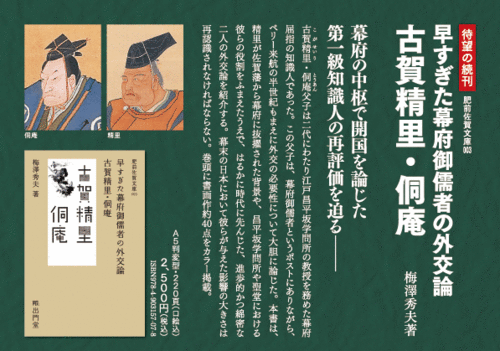 出門堂の待望のシリーズ「肥前佐賀文庫」の第3弾、
出門堂の待望のシリーズ「肥前佐賀文庫」の第3弾、肥前佐賀文庫003 早すぎた幕府御儒者の外交論 古賀精里・侗庵
がまもなく発刊となります。
6月20日発行予定です。
古賀精里は佐賀藩校弘道館の初代校長となり、のちに昌平坂学問所(昌平黌)という幕府の学校の教授となる異例の経歴を辿りました。
息子の侗庵は父精里と共に佐賀から江戸に移り、同じく昌平黌の教授となりました。
親子二代で昌平黌の先生という例はほかにはなかったようです。
現在の学校の教科書にはページの隅に「(注)」でしか取り上げられていない精里・侗庵親子ですが、彼らが幕府の中枢にありながら、ペリーが浦賀にやって来る半世紀も前に進歩的で綿密な外交論を唱えていたことが本書には紹介されています。彼らの先進的な考え方が幕末の日本にどれだけ大きな影響をあたえたか、再認識されるべきだと思います。
巻頭には二人の書画など約40点をカラー掲載している贅沢な一冊です。
刊行までもうしばらくお待ち下さい。
Posted by 出門堂 at 18:00 | Comments(0) | 今日のおすすめ
2008年06月02日
枝吉神陽が会った人々7 玉蟲拙斎
函館の山形道文先生(函館漢詩文化会会長)が北海道新聞に5回にわたるインタビュー構成で、堀利煕を中心に「堀奉行と箱館の侍たち」という記事が掲載され、その第4回目(2008年3月27日)に玉蟲拙斎について語っておられます。山形先生の了解を得て紹介いたします。
箱館八景扇面図の侍はあと二人。姫路藩出身の菅野潔は、昌平坂学問所の塾長に抜てきされるほどの秀才で、蝦夷地の紀行文「北遊乗」を記しました。扇面図では、七重村(現七飯町)周辺の風景を漢詩「七重晴嵐」として詠んでいます。
菅野は、箱館奉行の堀利煕が「誠終舎」と命名し、開設した庶民教育施設「心学講釈所」で孟子を講義しました。菅野は扇面図の侍の中で最初に江戸に帰ります。しかし、江戸には安政五年(一八五八年)から翌年にかけ、大老井伊直弼による政治弾圧「安政の大獄」の嵐が吹き荒れ、「国許永蟄居」の厳罰を受けたのです。
扇面図の最後の一人、仙台藩出身の玉虫左太夫は、後の戊辰戦争の末に非業の死を遂げる侍です。漢詩「山背帰帆」では、山背泊(現函館漁港)の風景を詠んでいます。
海湾縈曲擁牛山
山上模糊雲半間
尤愛漁村斜日景
千颿一送捲波還
「海は湾曲して臥牛山を抱き、山上はかすみ雲間に見え隠れする。何より素晴らしいのは山背泊漁村の夕暮れの風景。多くの船が一斉に波をけたてて港に戻ってくる」
玉虫も、昌平坂学問所の塾長を務め、諸藩の大名まで教えた人物。安政四年(一八五七年)、堀の近習役として蝦夷地の探索に付き従いました。玉虫の紀行文「入北記」には、扇面図の侍をはじめ、島義勇、松浦武四郎、榎本武揚らと交友したことが記されています。
万延元年(一八六〇年)一月、外国奉行を兼務していた堀の推挙で、日米修好通商条約批准書交換で米国に向かう使節団の一員に選ばれ、米国軍艦ポーハタン号で太平洋を渡ります。首都ワシントンで大統領ブキャナンに接見した後、アフリカ各地や香港に立ち寄りながら九ヵ月後に帰国。堀への報告書として世界一周の見聞記「航米日録」にまとめました。
巡察参加も海外渡航も堀の後押しによるもの。堀は玉虫の才能を愛し、将来の活躍を期待していたことでしょう。
時は流れ、大政奉還の後に江戸幕府は瓦解。戊辰戦争で薩摩藩、長州藩を中心とした新政府軍が北上する中、玉虫は東北、北陸の三十一藩による奥羽越列藩同盟の軍事局副頭取として戦い、敗れます。旧幕府軍の艦隊を率い「蝦夷共和国」建設を目指す同士、榎本武揚との合流を果たせず抗戦の首謀者として捕らえられました。
そして玉虫は明治二年(一八六九年)四月、牢前切腹を命じられ、首を落とされます。親交の深かった福沢諭吉は「福翁自伝」で、政府の戦後処理について「久我大納言を勅使に下向させたが、あろうことかあるまいことか仙台藩士が生首を七つ持ってきた」と玉虫の最期の様子を描き、早過ぎる死を嘆きました。
共に蝦夷地を巡察した榎本は明治政府に重用され、後に外務大臣、農商務大臣などを歴任します。もし、玉虫が戦禍を生き永らえ、蝦夷地に渡っていたら・・・。
と述べておられます。玉蟲は神陽の従弟・島義勇にも接触したことがわかります。
巻頭で上げておられる菅野白華は、このブログ「枝吉神陽が会った人々2」で紹介しました。ブログの公開1日後にインタビューが掲載されているのは偶然です。もちろん私のは孫引きですからいっしょにしてはいけませんが……。山形先生のような方がこうした人物を丹念に調査しておられることに敬意を表します。
Posted by 出門堂 at 10:00 | Comments(0) | 枝吉神陽が出会った人々
2008年05月31日
編集見習い日記-その6-
出門堂に入門してはや一年、私が企画の段階から関わってきたはじめての本が、まもなく刊行されます。昨年、『佐賀読本』が書店に並んでいるのを見たときにもうれしさがこみ上げてきたのを覚えていますが、やはり一冊の本ができあがっていく過程をはじめからみてくると、一入の感慨があります。
このエッセイには、昭和のはじめ、佐賀市の本庄という小さな町に育った少女が出会った日々の出来事がつづられています。本書のいたるところにあふれる著者の思いは、同じ頃を生きた人々はもちろん、当時を知らない私たち若い世代にもしっかりと伝わってきます。
提灯を片手に暗い夜道をいっしょに歩いてくれた小父さんのこと、いまも心のひとすみにある父と「私」の「狸の薬局」のこと、少女の日常のひとつひとつに触れると、彼女自身や周りの大人たちのやさしいぬくもりに包まれるようです。希薄になってきたといわれる「大人」と「子供」のつながりが、昭和のはじめ、少女の周りにたしかにあったのだということがひしひしと感じられます。あたたかくて、なつかしくて、そして少しせつない36の掌篇です。
6月20日に発行予定の出門堂の新刊です。ご期待下さい。

著者 小山内富子
挿絵 緒方義彦
目次
なしてかの道
大人はしっきゃ親代わりたい
私が斜視だったころのことなど
寒稽古
メダカの御冥福
功名の雨傘
キャーモンの日
出直し喧嘩
戻り橋
もぐら打ち
徒らに机上の装飾とする勿れ
空を飛んだ鯛
村の巡査と一升の米
ぜんもんさんの宴
父の兄弟と古代オリンピック
狸の薬局
ホッテントットの化粧料
千人針と野菜爆弾
さんとく銀行
毬子を抱いて戻った友達
父の女装
色彩二題
鼈甲の煙草ケース
魚の哲学
文字のない墓石
遠い眺め
海辺のハイジ
方言賛歌
ピンクの雨
虚構であったとしても
「にゃーごとあろう」父の後ろ姿
乳母車
道を急ぐことはない
菩提寺の本堂で
窓のない蔵の窓
五文字の電報
Posted by 出門堂 at 09:36 | Comments(0) | 編集見習い日記
2008年05月15日
「お玉ヶ池種痘所」開設150年
この「お玉ヶ池種痘所」は現在の東京大学医学部の前進といわれています。開設と運営については、伊東玄朴(佐賀県神埼町仁比山出身)を中心とする蘭方医たちが尽力していたそうです。
そして、天然痘治療に大きな成果をみせ、撲滅へのきっかけとなる牛痘接種を日本ではじめて成功させたのは長崎出身で佐賀藩医であった楢林宗建です。牛痘接種成功への舞台裏を自ら医師である深瀬泰旦先生が『わが国はじめての牛痘種痘 楢林宗建』で詳しく書かれていますのでぜひご覧ください。
本文より少し抜粋
……蘭方医たちの牛痘接種法への憧憬は、日毎にたかまっていた。とくに佐賀藩では弘化三年の天然痘の大流行を機に、牛痘接種法への関心はいやが上にもたかまった。江戸在府の藩医伊東玄朴は、牛痘苗の移入を藩主鍋島直正に進言し、直正は長崎在住の藩医に痘苗入手の指示をあたえた。
当時の人の天然痘撲滅への強い思いが感じられます。
Posted by 出門堂 at 17:09 | Comments(0) | 今日のひとこと
2008年05月04日
枝吉神陽が会った人々6 五十嵐三省
さて、この五十嵐三省ですが、「五十嵐三省墓誌」なるものがあり、『事実文編』七六に収録されています。撰文は木原元礼です。それによると、
文政2年(1819)~明治7年(1874)。名を儀一、別号を愛山。常陸土浦の人。土屋氏に仕える。木原とともに藤森弘庵のもとで学んだ。昌平坂学問所にも留学した。
ということがわかります。このような人物たちがどの程度顕彰されているのか?
常陽新聞新社『民話一○○話 土浦ものがたり』の中に取り上げられているようですが未読です。
神陽の足取りを追ってみると、昌平坂学問所の人物が藩をこえて交際が密であったことがよくわかります。
Posted by 出門堂 at 09:00 | Comments(0) | 枝吉神陽が出会った人々
2008年05月01日
一年ぶりのリベンジ
ご存知の方も多いと思いますが、ここは湛然和尚が晩年住まいとしていた跡です。湛然和尚とは『葉隠』の口述者である山本常朝の師として大きな影響を与えた人です。現在は、このような塔がたててありました。

実は、約一年前にも出門堂発行の「老いと死の超克――わが葉隠」の取材でこの場所を探していました。1時間以上も近辺を探し回ったあげく、たどりつくことができずに諦めたのですが、今回は難なく行きつけました。というのも、「華蔵庵」入口に去年の取材時にはあきらかになかった、立派な案内板が設置されていて容易に発見できたのです。どなたか、同じ思いをされて設置していただくことになったのかわかりませんが、名古屋からのお客様を案内していたので非常に助かりました。
「華蔵庵」は杉林に囲まれた小高い山の中にありました。鳥の声と風にゆれる杉の葉の音しか聞こえない静かな場所です。ここで湛然和尚と山本常朝はどんな話をしていたのか……
去年の取材時に同じ大和町にある石田一鼎の閑居跡も訪れたのですが、ここも探しあてるのに苦労した場所でした。全ての史跡の整備がなされるのは難しいかも知れませんが、郷土の遺産を大切にしていきたいと思った一日でした。
取材箇所もろくにたどり着けないなんて……まだまだ詰めがアマイ編集の日々です。
ちなみに「華蔵庵」はこちらです。
国道263号線を三瀬峠方面へ向かって大和町の三反田交差点を左折すると右手に画廊があります。
そのすぐ脇の小道を登って左の道へ進み、ばらくしたら「華蔵庵」の案内がみえます。
Posted by 出門堂 at 15:47 | Comments(0) | 取材日記
2008年04月21日
編集見習い日記-その5-
ムツゴロウは地域のシンボルマークにもなっていますし、また昨年小社で刊行した『佐賀読本』の編集にあたってもたくさんの写真を見ていたので、すっかり見たつもりになっていましたが、じつは私はそれまで本物のムツゴロウを見たことがありませんでした。そして、見たことがないというその事実に、はじめて気がついたのです。生まれは長崎、現在は佐賀、有明海にこれほど近い場所にいながら、いかにもうかつでした……。
残念ながら近くまで行くことはできませんでしたが、思い思いに飛び跳ねたり、小さいのを威嚇したりしている姿はなんともほほえましく、いつまでも眺めていたいと思ったのでした。
Posted by 出門堂 at 13:00 | Comments(1) | 編集見習い日記
2008年04月15日
枝吉神陽が会った人々5 安藤伯恕
今回もやはりよくわからない人物です。
宇和島の安藤伯恕。『枝吉神陽先生遺稿』に記された落款によると、「宇和島安藤知忠」とあることから、宇和島藩儒臣の安藤霞園という人ではないかと考えています。この人の父は安藤観生、字を伯容というらしく、そうではないかと想像しています。毎度のことながら、ご教示を待ちます。
当時の宇和島藩主は伊達宗城です。佐賀藩主鍋島直正とは従弟にあたり、関係も親密だったようです。家臣の間にも何か近しいような気持ちがはたらいたとも想像できます。
安藤伯恕が神陽に贈った詩。
鴉声鐘響暁沈々。唱罷驪歌涙湿襟。三四年間交友意。数千里外別離心。斜陽桑海雁行遠。落木蘇山秋気深。定識旅亭孤宿処。夢魂猶在茗渓潯。
送世徳枝吉君西帰。辱弟南豫安藤知忠拝。
Posted by 出門堂 at 10:00 | Comments(0) | 枝吉神陽が出会った人々
2008年04月12日
展覧会にいってきました
現在、「平成19年度新収蔵品展」というコレクション展が行われており、書や絵画、伝統工芸品など初めて観るものも多く大変興味深い展覧会でした。
なかでも、興味を引かれたのは三代藩主鍋島綱茂の絵画です(テーマ展「孔子をみる」にもありました)。緻密に細い線まで描かれたその絵画は画家の作かと思うほど繊細に描かれており、佐賀藩主の幅広い教養の高さを思わされました。
また、副島種臣の書も新たに収蔵されており迫力の作品でした。
時間があまりなくゆっくり鑑賞することができませんでしたが、雨の休日にでも(雨でなくとも)もう一度でかけてみたいと思う展覧会でした。
博物館のほうではテーマ展の「孔子をみる――えがかれた聖人――」も開催中でした。
来週4月18日(金)は多久市の多久聖廟で春の「釈菜」も行われるようです。今年は多久聖廟創建300年にあたり、これを機に『論語』について見直してみるのもいいですね。
詳しくは、コレクション展「平成19年度新収蔵品展」「孔子をみる――えがかれた聖人――」。
Posted by 出門堂 at 17:54 | Comments(1) | 今日のおすすめ
2008年04月09日
編集見習い日記-その4-
外山滋比古『思考の整理学』(ちくま文庫、1986)
タイトルに惹かれ手にとって眺めていると、編集長も若いころに読んだ本だというのですぐにその場で購入しました。しかし、この数ヶ月間一度もページを開かれることなく、自宅の本棚に眠っていた一冊です。
4月1日(火)付の朝日新聞に、この本の著者である外山氏のコラムが掲載され、ふと思い出して読み始めました。ぱらぱらとページをめくりながら、気になったところを少しずつ読んでいるだけですが、それだけでもずいぶん頭の中がすっきりした、というと、安直でしょうか。しかし実際、そんな気がするのです。
「忘却恐怖症」。コラムにはこのような言葉がありました。これについて、氏は前掲書の中で次のように述べておられます。
こどものときから、忘れてはいけない、忘れてはいけない、と教えられ、忘れたと言っては叱られてきた。そのせいもあって、忘れることに恐怖心をいだき続けている。(中略)倉庫としての頭にとっては、忘却は敵である。博識は学問のある証拠であった。(中略)どんどん摂取したら、どんどん排泄しないといけない。(中略)頭をよく働かせるには、この“忘れる”ことが、きわめて大切である。
そして、このように結論づけられています。
忘れるのは価値観にもとづいて忘れる。(中略)価値観がしっかりしていないと、大切なものを忘れ、つまらないものを覚えていることになる。これについては、さらに考えなくてはならない。
最後にしっかりと釘を刺しておられる。さすがですね。まずは「しっかりとした価値観」を持つ。これがないと、いつも自分自身に振り回されてばかり、ということになりかねません。自分のよりどころとなるものを作っておかねばと思う今日この頃です。
Posted by 出門堂 at 09:00 | Comments(0) | 編集見習い日記